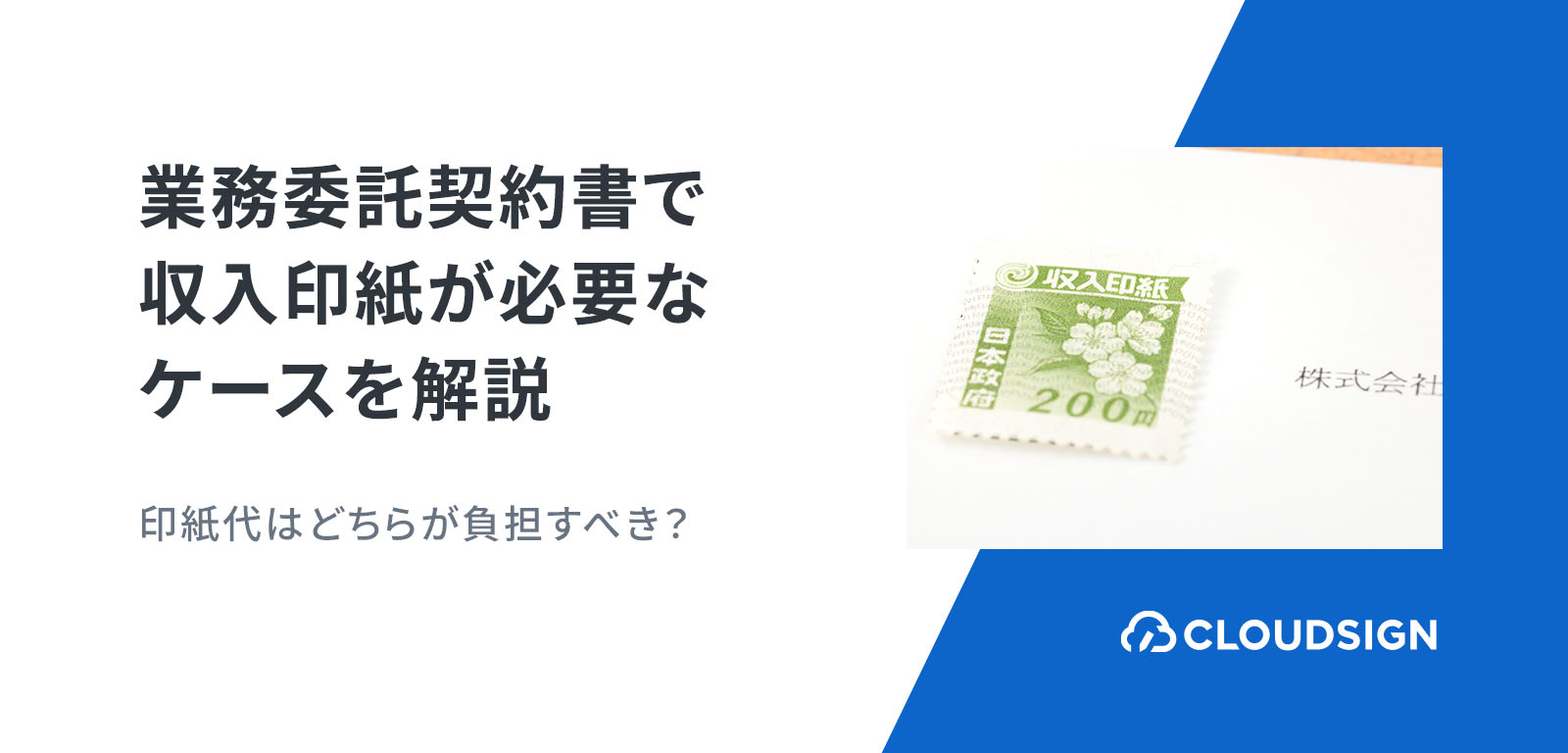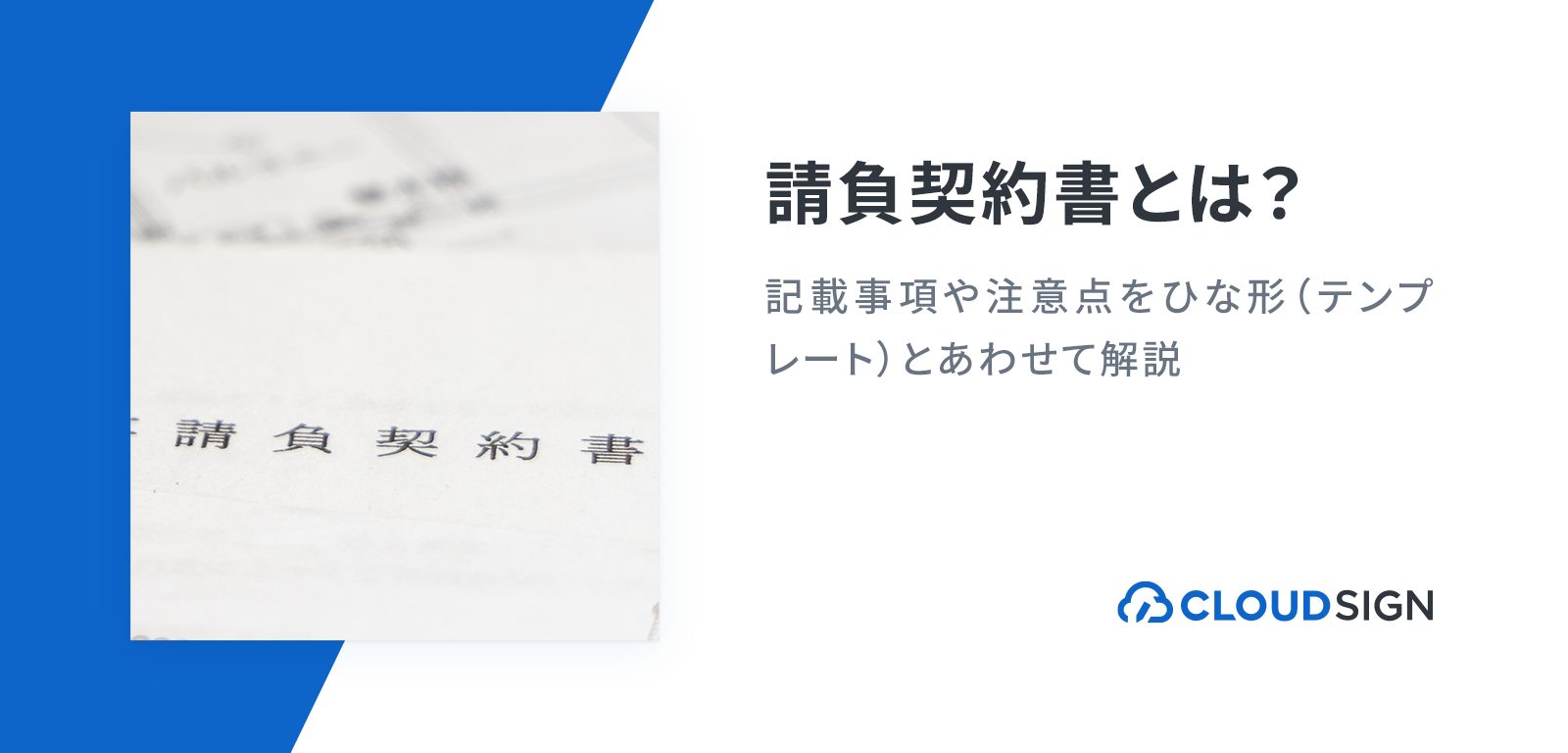業務委託とフリーランスの違いとは?業務委託契約を締結するメリットや注意点を解説

本記事では、業務委託とフリーランスの違いや、業務委託契約の種類などについて詳しく解説します。また、記事後半ではフリーランスが業務委託契約を締結するメリットや注意点も紹介します。
本記事で業務委託とフリーランスの違いを解説する背景として、コロナ禍や働き方改革などによるリモートワークの普及もあり、多様な働き方を選択する労働者が増えており、業務委託契約を積極的に取り入れている企業も目立ってきていることや、2024年11月にフリーランスの立場を保護する目的でフリーランス新法が施行されたこともあり、改めて業務委託契約の内容を見直している企業の担当者様も多いことが考えられるためです。
これから業務委託契約を締結する予定の方はぜひ参考にしてください。
目次
業務委託とフリーランスの違いとは
「フリーランス」と「業務委託契約」は混同されやすいですが、「フリーランス」として活動されている方が企業や組織と結ぶ契約が「業務委託契約」という関係性があります。つまり、フリーランスとは「働き方」を指し、業務委託契約とは「契約形態」を指す言葉であるといえ、似た文脈で使われますが全く違う意味を持ちます。
参考数値として、2023年の総務省統計局の発表によると、日本国内の有業者のうち本業がフリーランスの数は209万人となっており、有業者に占める割合は3.1%となっています。
まずここでは、「フリーランス」と「業務委託」のそれぞれについて、言葉の定義や使用方法を紹介します。
業務委託契約とは
業務委託契約とは、企業が業務の一部またはすべてを外部の個人や組織に委託して、その対価として報酬を支払う契約を指します。
一般的に、企業は労働者を従業員として雇い入れ、従業員とは雇用契約を結びます。雇用された労働者は、労働基準法をはじめとした労働法規によって最低賃金や残業代などの保障がある上、雇用保険や社会保険への加入も可能です。
ただし、従業員は使用者である企業の指揮命令下で業務にあたる必要があり、契約に定められた業務時間や場所、業務範囲などを遵守しなくてはいけません。
その一方で、業務委託契約においては、業務の委託者と受託者は基本的に対等な関係にあり、受託者は業務を遂行するうえでの方法やスケジュールなどは自由に決められます。契約で定められた役務を果たしたり、基準を満たした成果物を期日までに納品したりできれば、その過程や業務にあたる場所や時間は指定されません。
ただし、雇用契約のように労働法規が適用されないため、最低賃金や休暇の保障がなく、収入が安定しづらいといったリスクがあります。
業務委託契約書やテンプレートについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
フリーランスとは
フリーランスとは、特定の企業に属することなく、仕事の案件ごとに企業と業務委託契約を結び、業務を遂行する働き方を指します。
フリーランス=個人事業主というイメージを抱かれがちですが、正社員として働くかたわら、業務時間外で他の企業と業務委託契約を結び、フリーランスとして副業をする人もいます。
法律によるフリーランスの明確な定義は存在しませんが、厚生労働省の「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」によると、「業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの」と定義されています。
一般的には「フリーランス=業務委託契約を企業と結んで働いている人」という認識で問題はないといえるでしょう。
フリーランスが締結する業務委託契約の種類
フリーランスは、一般的に企業と業務委託契約を締結して仕事を受注します。
実は、業務委託契約は法律などで明確に定義された言葉ではなく「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つを総称した呼び方であるにすぎません。
ここでは、業務委託契約に含まれる3つの契約形態について解説します。
請負契約
請負契約は、成果物の完成を目的とする業務委託契約の一種で、フリーランスが依頼者に対して具体的な成果物を納品することが求められます。
請負契約においては、依頼者が求める仕様や品質に基づき、完成した成果物が提供されなければ報酬が支払われません。具体例として、ウェブデザイナーが「ウェブサイトを作成し、完成品を納品する」といった業務を請け負う場合が挙げられます。
請負契約では、成果物が完成しない限り報酬を受け取ることができないため、フリーランス側には業務の進行管理やリスクの把握が求められます。また、完成した成果物に対して瑕疵(欠陥)があれば修正責任が生じるため、事前に成果物の範囲や仕様を明確にし、契約書に記載しておくことが重要です。
請負契約書について詳しく知りたい方やテンプレートが必要な方ははこちらもご覧ください。
委任契約
委任契約は、法律行為の遂行を目的とする契約形態で、フリーランスが依頼者のために特定の業務を代理または代行することを特徴とします。
具体例として、フリーランスの行政書士が「会社設立に必要な書類の作成と申請手続きを代行する」といった業務を行う場合が該当します。委任契約においては、結果ではなく、業務遂行そのものに対して報酬が発生するという特徴があります。
委任契約では、フリーランス側に依頼者の意図や目的を的確に理解し、忠実に業務を遂行する義務があります。また、受託者には善管注意義務が課せられるケースが一般的であるため、依頼者に不利益が生じないよう、専門的な知識やスキルを活用して行動することが求められます。
準委任契約
準委任契約は、法律行為以外の業務を遂行する契約形態で、フリーランスが依頼者の指示に基づき特定の作業を行う場合に用いられます。
具体例として、フリーランスのエンジニアが「システムの運用サポート」や「データ入力作業」を行う業務などが挙げられます。こちらも委任契約と同様、成果物ではなく業務遂行に対して報酬が支払われます。
準委任契約では、業務遂行の義務はあるものの、請負契約のように成果物の完成を保証する必要はありません。ただし、契約内容や業務範囲が曖昧だとトラブルの原因になるため、どのような作業をどの期間で行うかという諸条件を契約書に明確に記載することが重要です。
準委任契約についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
フリーランスが業務委託契約を締結するメリット
フリーランスが業務委託契約を締結するメリットは、主に以下の4つです。
・高い自由度で業務を遂行できる
・上司や同僚等との人間関係に悩む心配が少ない
・得意分野の業務に専念できる
・複数社から同時に報酬を得られる
高い自由度で業務を遂行できる
フリーランスの業務委託契約では、業務遂行の自由度が高いことがメリットです。
契約内容に基づき、納品期限や成果物の基準が明確に定められている場合でも、その過程については基本的に委託者から指示されないため、自分に最適なペースや方法で業務を進めることができます。
たとえば、働く時間帯や場所を自由に選べるため、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。これにより、育児や介護など、個人的な事情を抱える方でも効率よく働くことができます。
一方で、自己管理能力が求められるため、スケジュール管理やタスクの優先順位付けを適切に行うスキルが重要となります。
上司や同僚等との人間関係に悩む心配が少ない
業務委託契約を締結して働くフリーランスは個人として業務を推敲するため、職場における上司や同僚との人間関係に悩む心配を軽減できます。
業務委託契約では、業務内容や報酬に関する取り決めが契約書に明記されていますが、依頼者と受託者の関係はあくまで対等なものとなります。そのため、職場のような日常的な上下関係や派閥争い、雑務の押し付けといったストレス要因から解放されるメリットがあります。
フリーランスは安定して仕事を受注するために一定の営業活動をする必要があるケースもありますが、飲み会や接待なども通常のサラリーマンと比較すれば少ないと言って差し支えないでしょう。
特に、人間関係の煩わしさが仕事の満足度に影響することが多い人にとっては、この点がフリーランスになるうえでの大きな魅力になり得ます。依頼者との関係においても、契約内容に基づいたプロフェッショナルな関係が求められるため、余計な感情的負担が少なくなります。
得意分野の業務に専念できる
業務委託契約では、フリーランスとしての得意分野に特化した業務を選び、専念できるのが魅力です。
業務委託契約においては契約内容が明確であるため、自分が最も得意とする分野やスキルに基づく仕事を中心に引き受けることが可能です。
例えば、ウェブデザインに特化したスキルを持つフリーランスが、特定の企業からウェブサイト制作の仕事のみを受託するといったケースが典型的です。また、契約範囲外の雑務を依頼される心配が少ない点もメリットです。
これにより、自分の専門性を活かしながらクライアントに価値を提供できるだけでなく、成果物の質の向上も期待できます。
また、自分の興味やスキルに合った業務を選ぶことで、仕事に対するモチベーションを維持しやすくなるでしょう。その結果、キャリアの専門性を深め、長期的な成長や報酬アップにもつながる可能性もあります。
複数社から同時に報酬を得られる
フリーランスの業務委託契約では、複数のクライアントと契約を結ぶことが可能であり、同時に複数社から報酬を得るという柔軟な働き方が実現します。収入源が一つの企業に限定されないため、収入が安定しやすくなるという点も期待できるでしょう。
この働き方の最大のメリットは、特定のクライアントからの契約終了や業務削減による収入減少リスクを分散できる点です。また、異なるクライアントと契約することで、幅広い経験を積み、新たなスキルを習得する機会も増えます。
ただし、企業・組織によっては、同業他社との業務委託契約を禁止する「競業避止義務」が契約に盛り込まれているケースもあるため注意しましょう。
フリーランスが業務委託契約を締結する際の注意点
フリーランスが業務委託契約を締結する際は、以下の3点に注意しましょう。
・税務処理などの事務作業を自分で行う必要がある
・契約が打ち切られるリスクがある
・労働基準法が適用されず最低賃金が保障されない
税務処理などの事務作業を自分で行う必要がある
フリーランスとして業務委託契約を締結する場合、税務処理や社会保険の手続きなどの事務作業を自分で行う必要があります。
雇用契約とは異なり、源泉徴収や年末調整を依頼主が代行してくれるわけではありません。確定申告を毎年行う必要があるため、最低限の税務知識を習得しておくことが重要です。
契約が打ち切られるリスクがある
業務委託契約は、一般的に契約期間が明確に定められており、依頼主の都合で契約が途中で打ち切られるリスクも伴います。
特に、契約書で途中解約の条件や通知期間が明記されていない場合、依頼主が予告なしに契約終了を通告する可能性もあります。これにより、収入が突然途絶える事態に直面するケースもありえます。
このリスクを軽減するためには、契約書に解約条件を明確に記載し、例えば「解約する場合は30日前に通知すること」といった取り決めが盛り込まれているか確認しておきましょう。また、複数のクライアントと契約することで、単一の契約終了による収入減少のリスクを分散させることも重要です。
労働基準法が適用されず最低賃金が保障されない
業務委託契約は雇用契約ではないため、労働基準法が適用されません。
その結果、最低賃金や労働時間の制限といった保障がないため、報酬額が非常に低くなるリスクがあります。特に、契約前に報酬の計算方法や支払条件が十分に交渉されていない場合、業務量に対して不公平といえる報酬が支払われる可能性もあるでしょう。
このリスクを回避するためには、契約書に報酬額や支払い条件を明確に記載されているか確認しておくことが重要です。支払額や支払い条件が明記されているかをしっかり確認し、自分の労働量やスキルに見合った報酬が得られるよう必要に応じて交渉しましょう。
フリーランスが業務委託契約を結ぶ際に気をつけるべきこと
最後に、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際に気をつけるべきことを紹介します。
報酬や業務内容が明記された契約書を締結する
フリーランスが業務委託契約を締結する際には、報酬や業務内容を明確に記載した契約書を作成することが非常に重要です。
口頭の合意だけで契約を進めると、後々トラブルに発展するリスクがあります。たとえば、業務範囲が曖昧な場合、依頼主から当初想定していなかった業務を追加で求められることや、報酬が支払われない事態も起こり得ます。
契約書には、具体的な報酬額や支払い条件などを明記するとともに、業務内容や納品物の範囲、納期も詳細に記載されている状態が望ましいです。
一般的には、フリーランスが業務委託契約を締結する際は、業務を依頼する企業側が契約書を作成します。企業側が作成した契約書をよく確認し、自分にとって不利な条件となっていないかしっかり確認しておきましょう。
著作権の所在を明らかにする
フリーランスがクリエイティブな業務に携わる場合、著作権の所在を契約書で明確にすることが重要です。
たとえば、デザインやコンテンツ制作といった成果物には著作権が伴い、その権利を誰が保有するのかを明記しないと、後日トラブルになる可能性があります。
特にフリーランスにとって、成果物をポートフォリオとして公開できるかどうかは非常に重要です。一般的には、成果物を伴う業務委託契約では著作権が依頼主に譲渡される場合が多く、ポートフォリオとして公開して次の仕事に繋げるといったことができないケースもあるので注意しましょう。
必要に応じて、著作権の譲渡についても交渉し、所在を明らかにしておくことが求められます。
まとめ
本記事では、フリーランスと業務委託契約の違いや、フリーランスが業務委託契約を締結する上での注意点などを詳しく解説しました。
フリーランスは、自由度の高い業務が遂行できる一方で、税務処理やタスク管理など様々な事務作業も必要となります。また、業務委託契約を結んだ際の契約書は、契約条件や報酬内容について確認するために適切に保管し、いつでも閲覧できる状態にしておくことが求められます。
電子契約サービスを利用すれば、クラウド上で過去の契約書をいつでも確認できます。フリーランスとして業務委託契約を締結している方は、ぜひ電子契約サービス「クラウドサイン」の利用をご検討ください。
「クラウドサイン」は、電子署名を電子ファイルに施し、スピーディーかつ安全に当事者間の合意の証拠を残すことのできる電子契約サービスです。導入社数250万社以上、累計送信件数 1000万件超の国内シェアNo1の電子契約サービスとして、業界業種問わず多くの方にご利用いただいております。
クラウドサインではこれから電子契約サービスを比較検討する方に向けて「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。
「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。下記リンクから無料でご入手できますので、ぜひご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
この記事を書いたライター