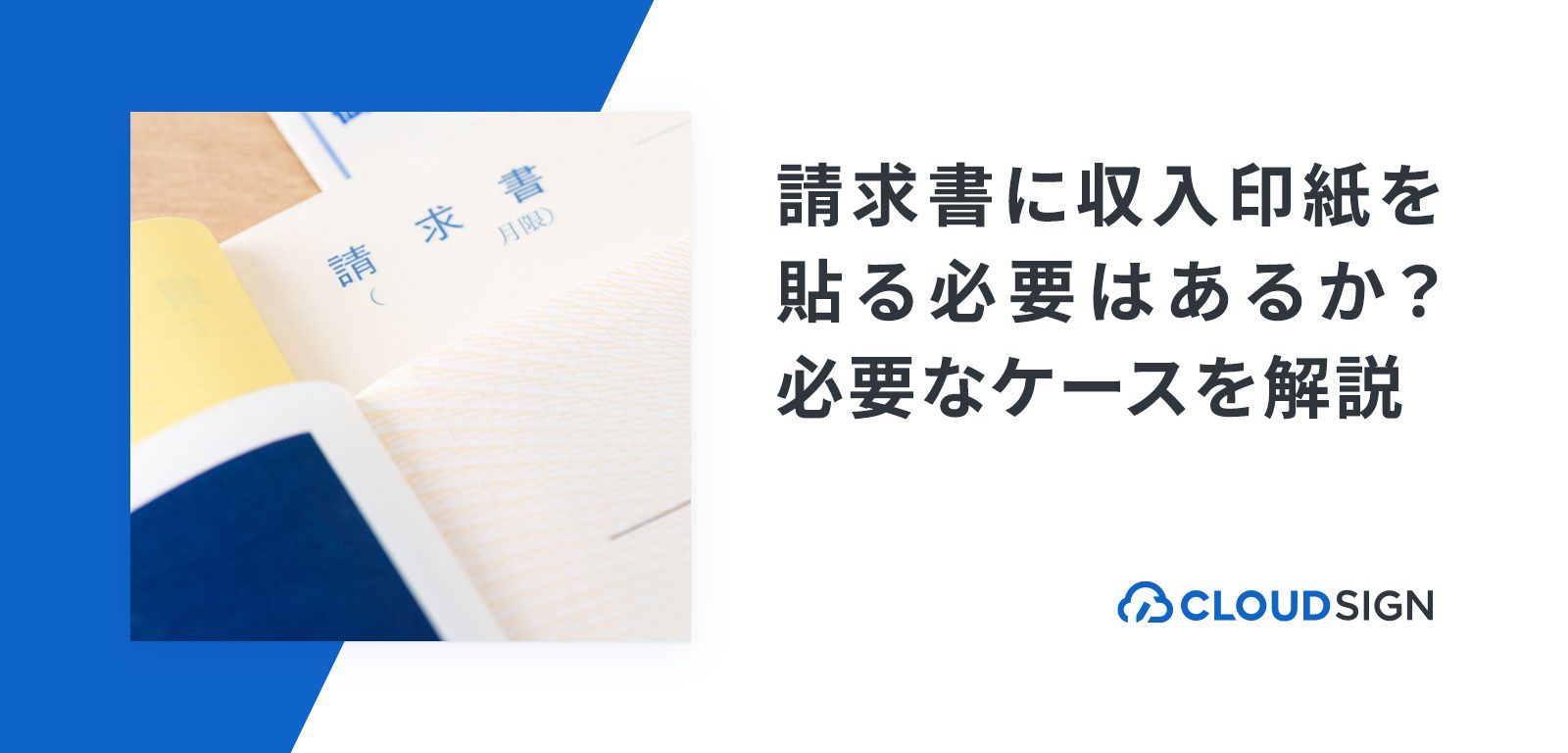請求書のハンコは必須?押印のメリットや電子化すべき理由を解説

ビジネスの現場では、請求書にハンコを押す習慣が根強く残っています。
しかし、実は法律上、請求書への押印は必須ではなく、印鑑が押されていない請求書でも支払い請求は可能です。昨今の電子契約の普及により、請求書にハンコを押すことへの必要性も問われるようになっています。
ハンコを押すことで取引先に対する信頼性を高めるといったメリットもありますが、業務効率の観点からは、押印作業の手間や郵送コストを削減できる電子化が有効だといえます。
本記事では、請求書の押印の必要性やメリット、そして電子化するべき理由について詳しく解説します。
目次
請求書へのハンコ(印鑑)の押印は義務?
結論として、請求書にハンコの押印は義務ではなく、押印がない請求書であっても正式なものとして扱われます。
前提として、請求書自体に法的な形式や記載事項などは定められていません。適格請求書(インボイス)でも押印は義務とされていません。
企業同士や業務委託先などとの取引において、請求書を作成せずに口頭やメールなどによって業務を依頼した場合でも、双方の合意があれば法的には契約は成立します。
しかし、請求書を発行していないと、業務内容や報酬などについて自社と取引先の間での解釈違いが発生する可能性があったり、税務調査の際に正しい取引があったことを証明するのが難しくなったりとさまざまなリスクがあります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、請求書を発行しておくのが企業間の契約などでは通例となっています。
以上のように、請求書はあくまでトラブル回避のために作成されるもののため、決まった形式はなく、ハンコの押印も義務ではありません。
請求書に記載が必要な項目とは
請求書の発行は法的に義務付けられておらず、請求書がなくても契約自体は成立します。
その一方で、請求書には証憑書類としての保管義務があり、仕入税額控除の根拠となるなど、税法や民法の適用を受けます。
さらに、インボイス制度(適格請求書等保存方式)により、2023年10月1日以降は適格請求書の要件を満たした書類でなければ、買い手は仕入税額控除を受けられなくなりました。
そのため、請求書を発行する際は、適格請求書としての要件を満たせるように、以下の項目については確実に記載しておきましょう。
・取引年月日
・取引内容
・取引金額
・軽減税率の対象品目である旨
・交付を受ける事業者の氏名または名称
・税率ごとに区分して合計した対価の額
・税率ごとの消費税額
取引先から適格請求書を求められた場合は、これらの事項を記載した請求書を発行する義務があるのでしっかりと押さえておきましょう。
【参考:適格証明書の記載事項 - 国税庁】
適格請求書(インボイス)でも押印は不要
インボイス制度においては、適格請求書発行事業者同士の取引の際、買い手側から適格請求書の発行を求められた場合は売り手側は適格請求書の発行および保存が義務付けられています。
しかし、適格請求書として必須の記載事項に印鑑は含まれておらず、押印がないものでも適格請求書として成立します。
ただし、ビジネスにおける信頼性の観点から、相手先から請求書への押印を求められるケースもあります。
トラブル回避のためにも、相手先から押印を希望されたら基本的には対応するようにしましょう。
押印は義務ではないが文書の信頼度が向上する
インボイス制度以降の適格請求書であっても、ハンコの押印は義務ではありません。その一方で、押印には文書の信頼度が向上するというメリットもあります。
会社印や角印などが押印されている請求書は、会社が正式に発行したという事実が一目でわかるため文書の信頼度が増します。
また、請求書への押印自体には法的義務はないとはいえ、慣習として多くの企業で長くおこなわれています。
そのため、企業によっては押印がない請求書は受け付けないといった姿勢をとっているケースもあるでしょう。
請求書に使用する印鑑の種類請求書に使用する印鑑の種類

請求書への押印は法的な義務はありませんが、取引先から求められた場合など押印するべきシーンもあります。
ここでは、請求書に押印する印鑑はどのようなものを使用すればいいか、請求書を発行する側が法人と個人事業主の場合それぞれについて紹介します。
法人の場合
法人は、一般的に「角印」「代表者印」「銀行印」などの印章を所有していますが、請求書に使用する印鑑としては、角印が一般的です。
角印とは、会社の名前が入った印章で、「社判(しゃばん)」とも呼ばれます。印鑑として正式な届出が必要なものではなく、認印と同様の位置付けとして多様な場面で使用されます。
具体的には、請求書のほか、見積書や発注書などの押印にもよく使われます。
一方、代表者印は法務局に登録された正式な印鑑で、重要な契約書などに使用されますが、印章の摩耗防止などの観点から業務上頻繁に発行される請求書への押印には不向きです。
同様に、銀行印も金融機関に届け出を出した正式な印鑑であり、金銭の出納や小切手の発行などで利用されます。
代表者印と同じく、摩擦防止や紛失のリスクを減らすために金融機関に関する重要な場面でのみ使用されるのが一般的であり、請求書の押印には利用されません。
個人事業主の場合
個人事業主やフリーランスの場合、請求書に押印する印鑑はどのようなものでも問題ありません。
しかし、プライベートで使用している印鑑とは別に、トラブルを回避する意味でもビジネス用に「角印」や「銀行印」を用意するのが良いでしょう。
個人事業主の角印は、代表者名と屋号をかたどった印鑑とするのが一般的で、請求書や領収書などの押印におすすめです。
また、事業用の口座を開設する際の手続きなどのために個人名や屋号が刻印された銀行印も用意しておきましょう。
請求書に押印する際の注意点
請求書への押印は法的な義務はありませんが、取引先から求められて押印する場合は以下の3点に注意しましょう。
・法人の場合は社名と少し重ねて押印する
・訂正印は使用しない
印鑑が鮮明に残るように押印する
請求書に押印する際は、印鑑がかすれたり、にじんだりしないように、鮮明に押すことが重要です。
請求書への押印自体に法的な義務はないため、押印の目的は信頼性の向上一点にあるといっても過言ではありません。
それにもかかわらず、印影が不明瞭だと、請求書の信用性が低下し、取引先に不信感を与える可能性があります。
特に、電子化が進んでいない企業との取引では、押印の品質が請求書の受理に影響を与えることもあるため、丁寧な押印を心がけましょう。
また、印影が不鮮明な場合、取引先から押し直しを求められたり、再発行が必要になることもあり、業務の手間が増えてしまうケースもあるでしょう。
押印をする際は、印鑑を水平に持ち、均等に力を加えながら押すようにしましょう。
捺印マットを使用すると、きれいな印影を残しやすくなります。インクが多すぎるとにじみ、少なすぎるとかすれてしまうため、朱肉の量にも注意が必要です。
法人の場合は社名と少し重ねて押印する
法人の請求書では、社名(会社名)の記載部分と少し重ねる形で印鑑を押すのが一般的です。
これは、押印が後付けされたものではなく、正式な書類として発行されたことを示すための慣習であり、契約書を作成する際の「割印」などと似ているといえます。
社名の一部に重なるように押印することで偽造が困難となり、請求書の真正性を証明する効果があります。
もし印鑑が社名と完全に離れてしまっていると、請求書が正式なものかどうか疑われることがあるため注意が必要です。
ただし、重ねすぎると社名が読みにくくなるため、バランスよく配置しましょう。
電子請求書の場合は押印が不要なケースが多いですが、印影をデジタルデータとして挿入する場合も、社名に重なる形で配置すると、紙の請求書と同様に信頼性の向上が期待できます。
訂正印は使用しない
請求書の内容に誤りがあった場合でも、訂正印を使用して修正することは避けるべきです。
訂正印とは、書類の誤字や金額の修正時に押す小さな印鑑のことですが、請求書などの正式な取引書類では、修正や訂正を避けるのが原則です。
理由として、訂正印が押された請求書は、改ざんや不正の疑いを持たれる可能性があるため、取引先に不信感を与えてしまうリスクがあります。
また、経理処理や税務申告時に、正式な請求書として認められない恐れもあるでしょう。
もし誤りを発見した場合は、新しく正しい内容の請求書を作成し、再発行するのが適切な対応です。
電子請求書を利用している場合は、データを修正し、改めて正しい請求書を送付することで、スムーズな処理が可能になります。
請求書の印鑑は電子印鑑でも問題ない?
請求書の印鑑は、電子印鑑でも問題ありません。
電子印鑑とは、紙に押印した印影をスキャンしたものなどを元にして、PDFファイルなどに電子的に押印できるようにした印鑑データを指します。
請求書の押印自体が法律上規定されておらず、どのような印鑑でも請求書に押印するうえでの意味合いは同じといえます。
そのため、紙面で印刷した請求書に押印せずに、電子化した請求書に電子印鑑を押印する形で請求書を作成しても法制度上は問題ありません。
ただし、電子印鑑を用いたり電子化した請求書を発行したりする場合は、トラブル回避のためにあらかじめ取引先の了承を得ておくようにしましょう。
電子印鑑の作り方
電子印鑑の作り方としては、主に以下の3つが挙げられます。
・フリーソフトやオンラインツールを使用して作成する
・Excelで作成する
電子印鑑を作成する最もシンプルな方法は、実際の印章を紙に押印し、それをスキャンしてデジタルデータとして利用する方法です。
まず、白い紙に印鑑を鮮明に押し、できるだけ影やかすれのない状態でスキャンします。
次に、Photoshopなどの画像編集ソフトを使用し、背景を透明化し、不要な部分を削除して印影を整えます。この加工をおこなうことで、電子文書上に重ねても自然な見た目になります。
作成したデータはPNGやGIF形式で保存すると、背景が透明なまま使用できるため便利です。
また、印鑑のデザインを自由に作成したい場合は、フリーソフトやオンラインツールを活用する方法があります。Web上で公開されているツールを用いると、楷書・行書・隷書など複数のフォントを選択でき、簡単にオリジナルの電子印鑑を作成できます。
Excelファイルで印鑑の縁となる図を作成し、その中に会社名などを入力するといった形で一から電子印鑑を作成することも可能です。
請求書などに押印する印鑑は法的な規定がなく、電子印鑑についても同様です。作成にかかる手間や自分の技術に合わせて、適切な方法を検討しましょう。
請求書を電子化するメリット
請求書への押印が義務ではないのと同じように、請求書自体も紙面で発行する必要はありません。
取引先の承認を得られるのであれば、請求書を電子化して発行することによって、以下のような大きなメリットを享受できます。
・ペーパーレスとなりコストを削減できる
・紛失などのリスクを回避できる
業務を効率化できる
請求書を電子化するメリットの一つは、業務効率の向上です。
紙の請求書では印刷、封入、郵送などの作業が発生し、多くの時間と手間がかかります。
一方で、電子化された請求書では、データを作成しメールや専用システムを通じて送信できるため、これらの手間が大幅に削減されます。
送付した請求書の確認や、受け取りの管理もデジタル上で一括して行えるため、対応漏れの防止にも繋がります。
さらに、電子請求書は検索機能を活用することで過去の取引履歴や金額を即座に確認でき、業務のスピードアップに寄与します。
特に、取引量が多い企業では、請求書管理にかかる労力を削減できるため、担当者の業務負担を軽減し、より重要な業務に時間を割くことが可能となるはずです。
ペーパーレスとなりコストを削減できる
電子化によるペーパーレス化は、請求書発行に関連するコスト削減に大きく貢献します。
紙の請求書を発行する場合、印刷用紙やインク、封筒の購入費用がかかるほか、郵送費も必要です。取引先が多い企業にとっては、これらのコストは非常に大きな負担となっているはずです。
一方で、電子請求書はデジタルデータとして作成されるため、消耗品や郵送費などのコストを完全にカットできます。
紙の請求書を保管するには、大量の書類を収納するための棚や倉庫が必要になりますが、電子化によりデータはクラウドやシステム上で管理可能となるため、保管スペースの問題も解消されます。
さらに、環境への配慮という観点からもペーパーレス化は重要であり、企業の持続可能性を高める施策としても評価されるでしょう。
紛失などのリスクを回避できる
紙の請求書は、紛失や破損のリスクが常に伴います。誤って廃棄してしまったり、保管場所が不明確で見つからなくなるケースも少なくありません。
一方で、電子請求書はデータとして保管されているため、クラウドや専用システム上での管理が可能となり、紛失の心配がほとんどなくなります。
適切にバックアップを取ることで、システム障害やデータ破損といったリスクにも対応できる体制を整えることができます。
さらに、アクセス権限の管理をおこなえば、特定の担当者以外が請求書に触れることを防ぐことができ、不正防止にも役立ちます。
このように、電子化は重要な取引書類を確実に保護する手段となり、取引先に対する信頼性向上にもつながるでしょう。
セキュリティを重視する方には電子署名できる電子契約サービスがおすすめ
本記事では、請求書への押印の必要性や、請求書の電子化のメリットなどについて詳しく解説しました。
請求書への押印は法律上義務ではなく、押印のない請求書であっても必要事項が漏れなく記載されていれば、税務処理上も問題ありません。
さまざまなコストや業務効率化のためにも、特別な事情がなければ請求書は電子データでの発行・管理がおすすめです。
また、請求書や契約書を電子化する際にセキュリティを重視する方には、電子印鑑よりも電子署名を利用した電子契約サービスがおすすめです。
特に、無料の電子印鑑にはセキュリティ対策が施されていないため、取引先との信頼関係が重要になるビジネスシーンでの利用は避けておくのが無難といえるでしょう。
セキュリティを考慮して契約書の電子化を実現するなら、クラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」の利用をご検討ください。
クラウドサインではこれから電子契約サービスを比較検討する方に向けて「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。
「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。
下記リンクから無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
この記事を書いたライター