契約書等の重要書類を適切に郵送する方法を解説
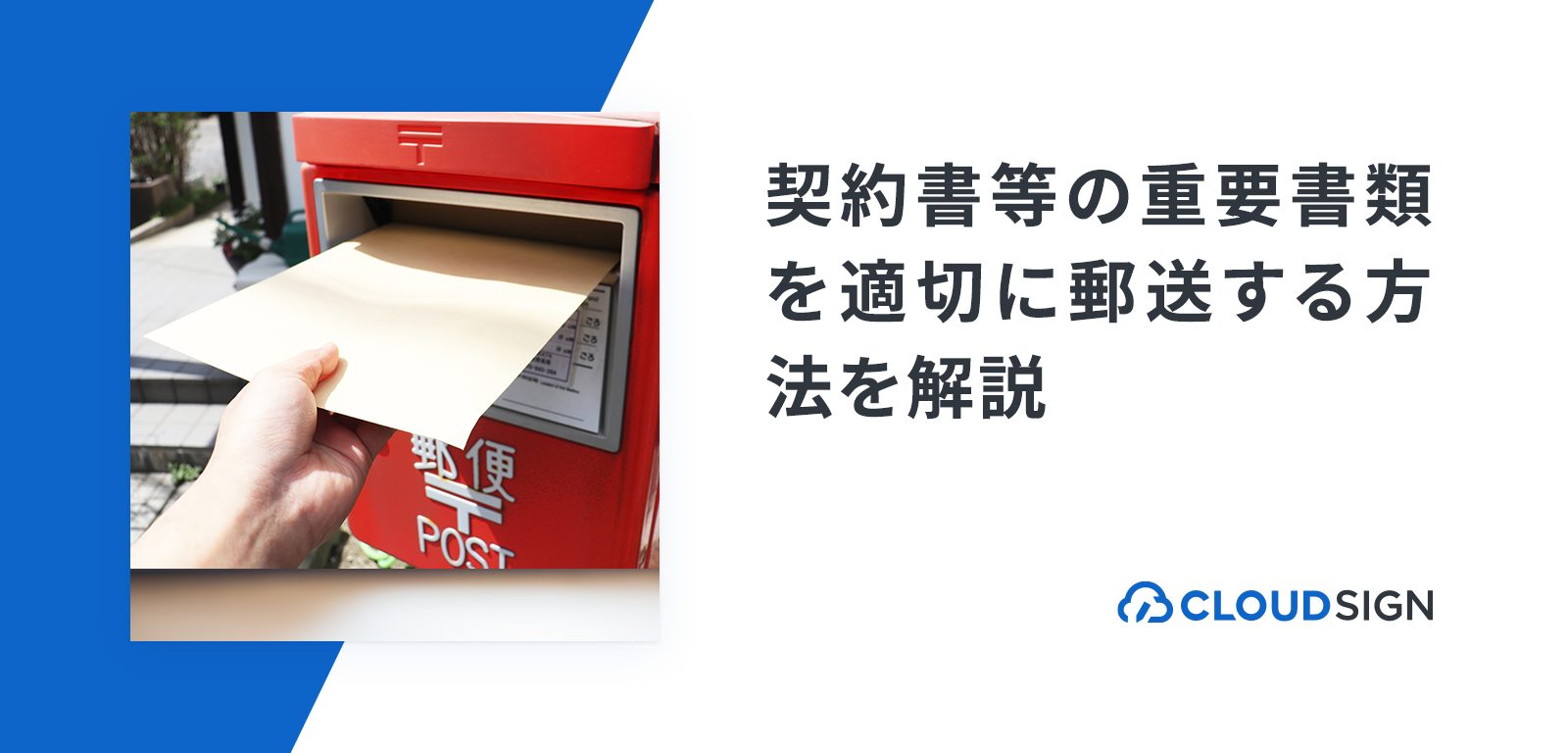
契約書などの重要書類を適切に郵送することは、ビジネス上の取引において不可欠であると同時に、十分な配慮と正確さが求められます。
当記事では、重要書類を適切かつ安全に郵送する方法を詳しく解説します。重要書類を郵送する前に知っておきたい法的ルールや郵送時の注意点など、様々なポイントを押さえながら適切な郵送方法を確認しておきましょう。
重要書類の郵送に関して知っておきたい法的ルール
送付したい重要書類が「信書」に該当する場合は、法律で定められた方法で送付する必要があります。
信書とは、契約書や納品書、履歴書、見積書のような書類に代表される「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」が当てはまります(郵便法第4条第2項、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第1項)。送付したい書類が信書に該当するかどうかを知りたい場合には日本郵便のQ&Aページ「信書に該当するものを教えてください」を確認しましょう。

信書の送付方法としては、日本郵便を利用する方法と総務省の許可を得た民間企業がサービス提供している「信書便」を利用する方法の2つが挙げられます。
上記以外の方法で信書を送ると郵便法違反となり、郵便法第76条で定められた3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
【郵便法(昭和22年法律第165号) (抜粋)】
第二条(郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。
第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
(2) 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなされる。
(3) 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
(4) 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
第七十六条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(2) 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
なお、上記(3)(4)にある通り、郵便法では運送営業者の信書の送達を禁じているため、宅配便に信書を含めることはできない点に注意しましょう。
重要書類を郵送する方法
重要書類を郵送する方法としては「普通郵便」「書留」「レターパック」が挙げられます。実際に利用する際には各サービス運営元の公式サイトなども事前に確認し、正しい手順を踏む様にしてください。
普通郵便
普通郵便は、書留や速達といったオプションサービスを付加していない、最も一般的な郵送方法です。定型封筒に書類を入れ、切手を貼って封をして送ります。
普通郵便は追跡ができないため、紛失や誤配達があっても損害の補償がありません。その点で重要書類の郵送方法としてはあまり向いていないと言えるでしょう。
書留郵便
書留郵便は、郵送した書類の到着完了を確認できるタイプの郵送方法です。受け取りの際は受取人の署名が必要になります。相手方が書類を受け取るまでの過程を追跡できるため、万が一相手に届かなかった場合でもその原因を特定しやすくなっています。また、郵便物の破損や届かなかった場合の補償も付帯しています。
重要書類を郵送する場合は、一般書留と簡易書留の2つの方法があり、料金や補償額も異なります。状況に応じて適切な方法を選びましょう。
【一般書留と簡易書留】
| 書留の種類 | 追加料金 | 補償額 |
|---|---|---|
| 一般書留 | +480円(基本料金に加算) | 10万円まで(5万円ごとに+23円で上限500万円補償) |
| 簡易書留 | +350円(基本料金に加算) | 5万円まで |
出典:書留|日本郵便
なお、令和5年10月1日に郵便物の特殊取扱料や荷物の付加サービスなどが値上げとなり、簡易書留料は320円から350円に値上げしました。最新の料金は日本郵便の公式サイトなどで確認する様にしてください。
レターパック
レターパックは専用の封筒でA4サイズ・4kgまでの荷物や信書を送ることができるサービスです。対面で相手に渡して受領印をもらえる「レターパックプラス」(全国一律520円)と郵便受けに届ける「レターパックライト」(全国一律370円)があります。
「レターパックライト」の場合、書類の厚さは3cm以内に制限されているため、3cm以上の書類を郵送する場合は「レターパックプラス」を選びましょう。
なお、レターパックの場合は書留と異なり受取人の署名は必要ありませんが、追跡番号をメモして書類の配達状況を確認できるようにしておきましょう。
2024年10月に郵便料金値上げの報道
2023年12月18日、総務省は郵便料金値上げの方針を示しました(参考:郵便料金値上げへ 定形封書110円・はがき85円|日本経済新聞)。その後の2024年5月21日のNHKの報道によると、値上げは今年10月に行われる見通しです。
25グラム以下の定形の郵便封書について料金の上限額を現在の84円から110円に26円引き上げ、はがきは現在の63円から85円に値上げする案が検討されていることがわかっています。また、レターパックや速達などの料金も値上げの検討がされていますが、詳細は不明です。
【郵便料金値上げの方針】
| 郵便物の種別 | 現在(2024年5月時点)の料金 | 検討中の料金 |
|---|---|---|
| 定型封書(25グラム以下) | 84円 | 110円 |
| 定型封書(50グラム以下) | 94円 | 110円 |
| はがき | 63円 | 85円 |
| レターパック | レターパックプラス:520円、レターパックライト:370円 | 未定 |
| 書留郵便 | 一般書留:480円を基本料金に加算、簡易書留:350円を基本料金に加算 | (書留郵便に関しては値上げの告知はなし) |
郵便料金の値上げにより、契約書をはじめとする重要書類を郵送する際のコストも大幅に増加することが予想されるため、書類の送付を郵送からオンラインに切り替えることも視野にいれてみてはいかがでしょうか。
なお、当社の提供するクラウド型の電子契約サービス「クラウドサイン」は書類の送信をオンラインで完結できるため、契約書等の重要書類も郵送費をかけずに送信することができます。電子契約の場合、印紙税もかからないため、書類郵送にかかるコストを大幅に削減可能です。書類郵送にかかるコスト削減のための電子契約導入を検討中の方はお気軽にご相談ください。
重要書類を郵送する際の注意点
重要書類を適切に送付するためには、郵送前の手続きを正確に行うことが不可欠です。特に契約書等の文書は、内容の正確性がビジネス取引や法的関係に大きな影響を与えるため、送付先の住所や宛名、書類の内容などを事前に確認し、ミスのないよう慎重に必要情報を入力・管理しましょう。
さらに、重要書類を送った後は、送信状況の確認も重要です。書留やレターパックを利用した場合は追跡番号を保管し、郵便局のウェブサイトやアプリを利用して送信状況を確認しましょう。
適切な手続きを踏み、慎重に送付準備を行うことで、重要書類を正確に送信し、相手方との信頼関係を築くことができます。送付前の手続きに注意を払い、慎重に重要書類を郵送することで、円滑なコミュニケーションと信頼性の高い取引を実現できるでしょう。
重要書類を送るなら電子契約サービスもおすすめ
ペーパーレス化の進んでいる昨今、従来の郵送方法だけでなく、電子契約サービスも選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。
重要書類を送る際には、法令の順守や郵送コストなどさまざまな観点で注意が必要になりますが、電子契約サービスを利用した場合は、郵送ではなくオンライン上での送信になるため、それらに注意する必要がなくなります。
電子契約サービスを導入する場合には、社内に存在する課題の整理や運用の定着化も重要になってきます。
当社の提供するクラウド型の電子契約サービス「クラウドサイン」は、導入時の課題解決や運用定着化のサポートも充実しています。
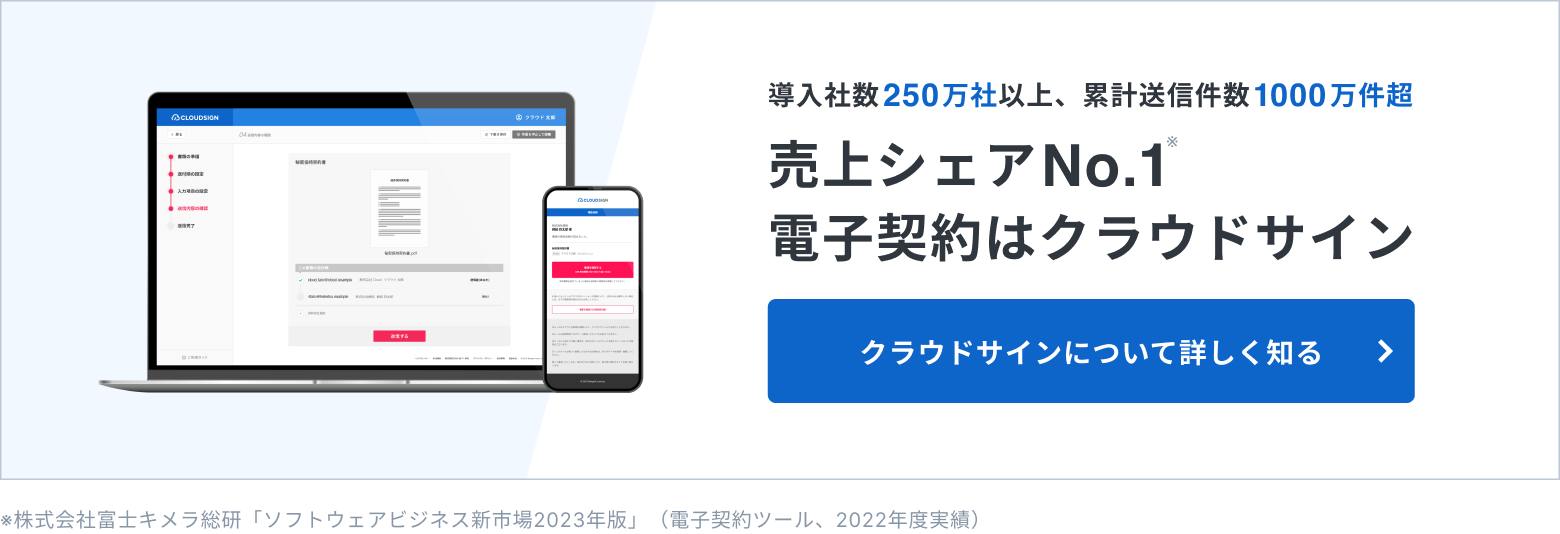
幅広い業界での導入実績があるため、コスト削減や業務効率化のための電子契約導入を検討中の方はお気軽にご相談ください。
なお、クラウドサインでは、電子契約で実現するコスト削減の方法を知りたい方にぜひご一読いただきたい資料「業務プロセスの無駄をなくすには?電子契約の導入からスタートする戦略的コスト削減」をご用意しています。
DXの観点からある程度早期に効果を出す短期的なコスト削減を「契約書類・事務のデジタル化」からスタートし、成功させる方法を事例を参考にしながら解説していますので、以下のリンクからダウンロードの上、ぜひ参考にしてみてください。
無料ダウンロード
こちらも合わせて読む
-
電子契約の運用ノウハウ

電子契約の代理署名は有効?代表者本人以外の押印有効性は
押印・署名 -
電子契約の運用ノウハウ
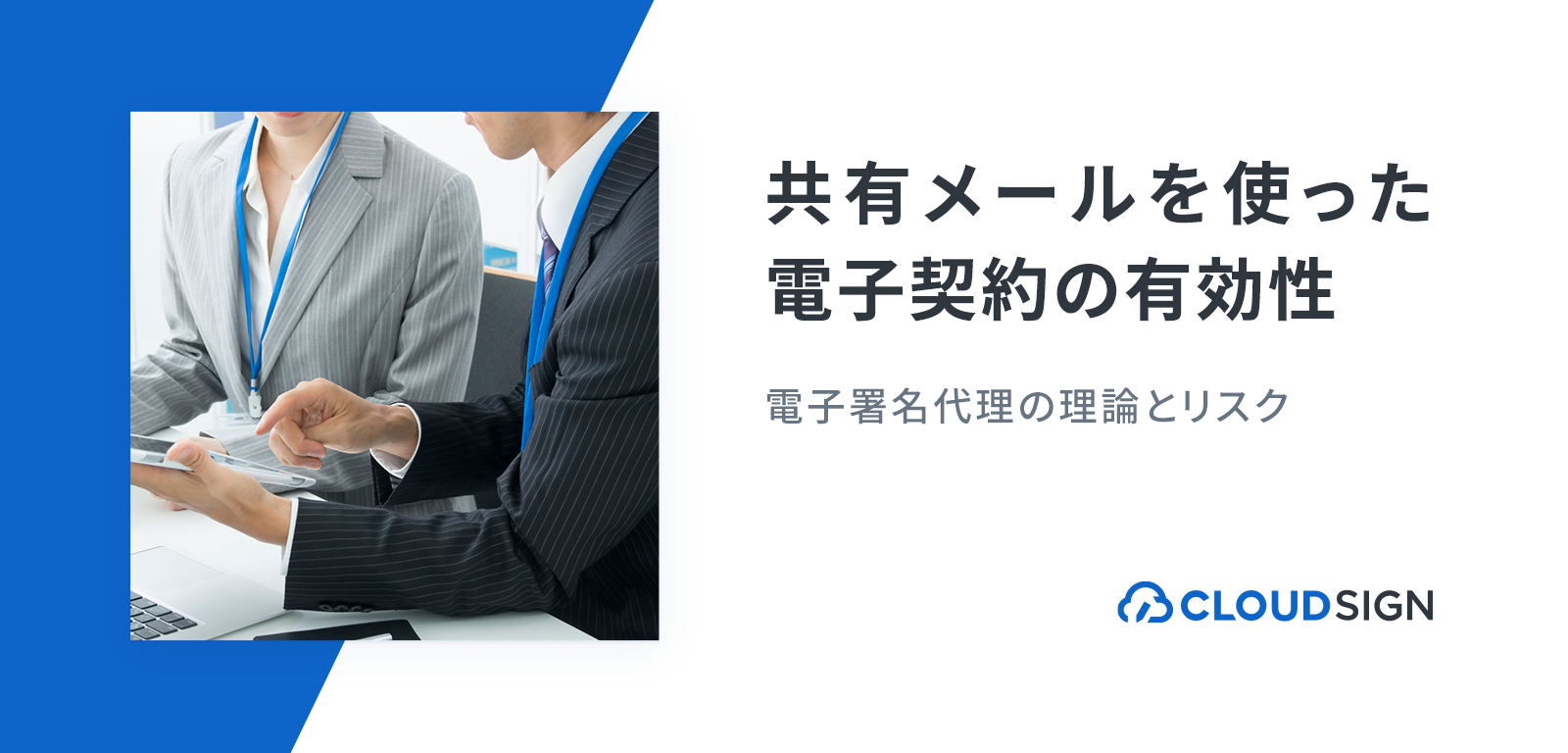
共有メールで電子署名のアカウントを共有する署名代理は有効か?
電子署名 -
電子契約の運用ノウハウ
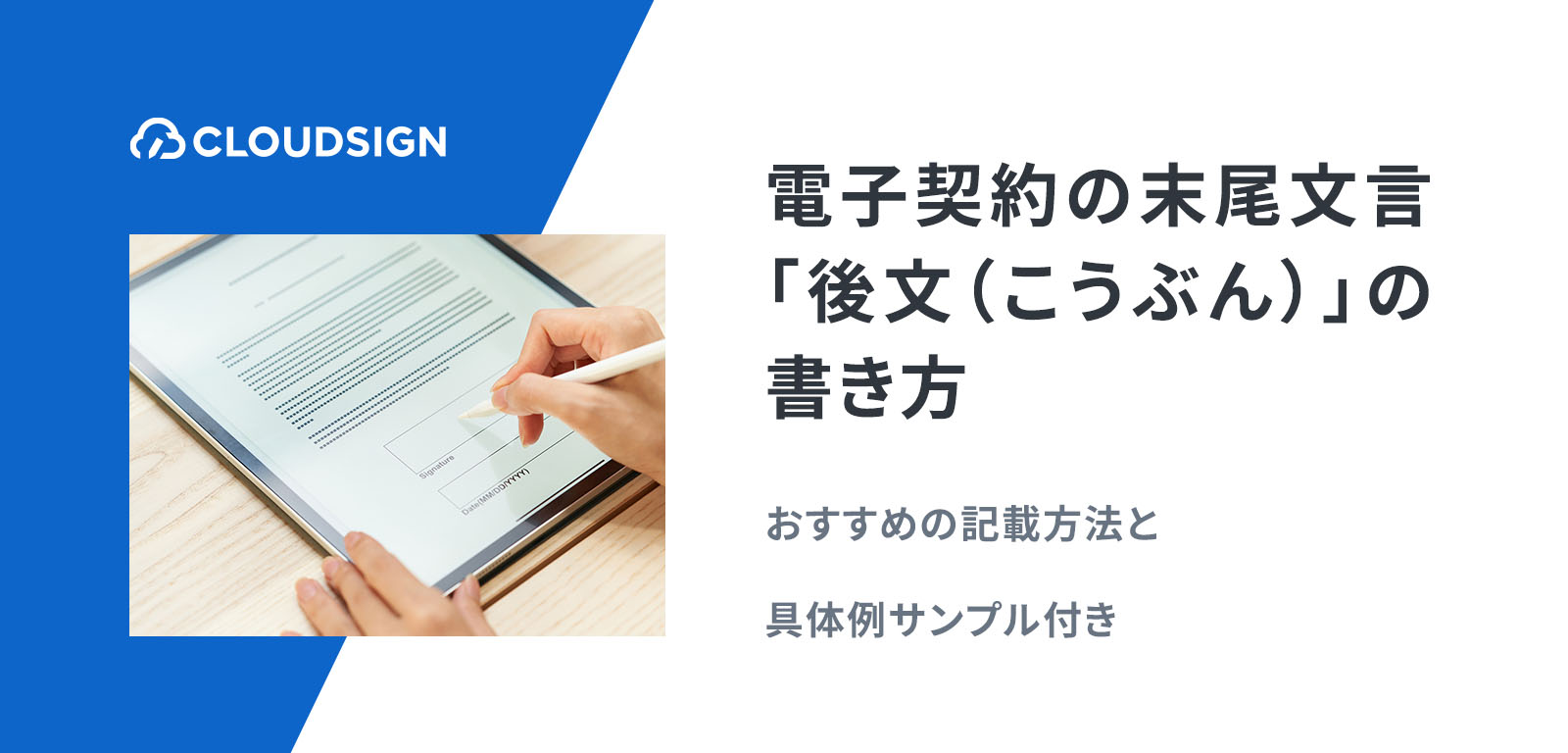
電子契約の末尾文言「後文(こうぶん)」の書き方【おすすめの記載方法と具体例サンプル付き】
契約書 -
電子契約の運用ノウハウ
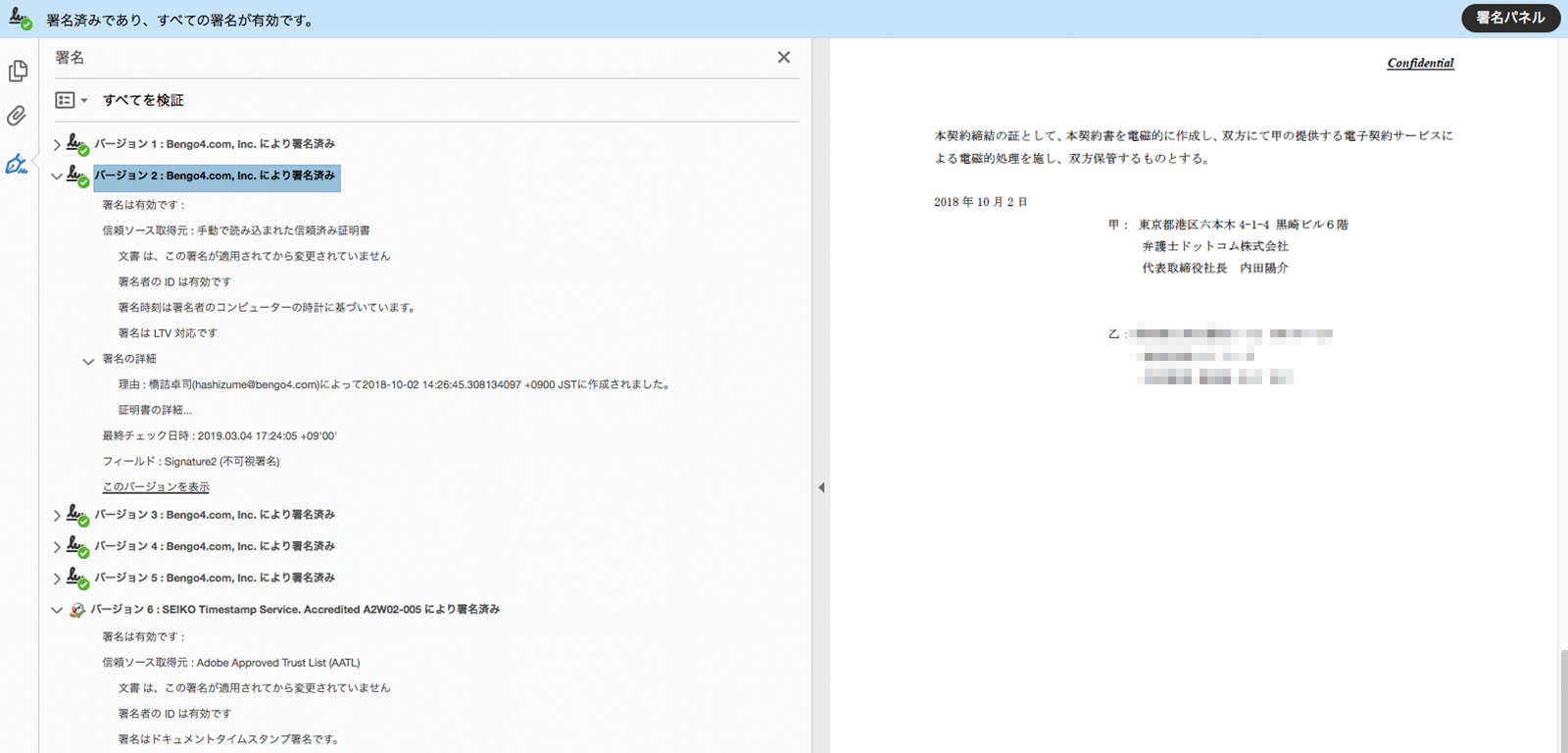
電子契約の当事者表示に住所の記載は必要か
契約書 -
契約に関する事例・判例・解説

労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】
契約書契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -
リーガルテックニュース
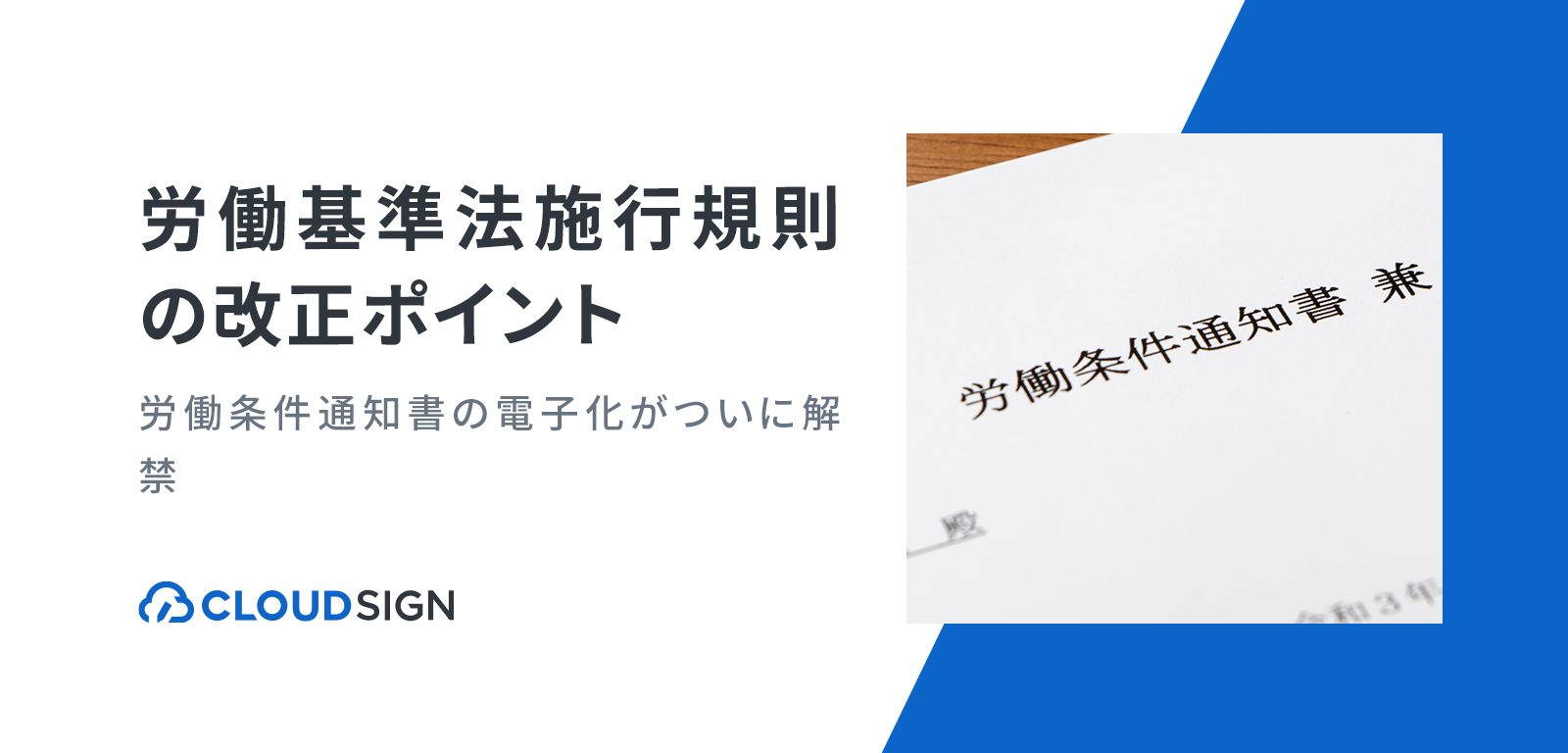
労働条件通知書の電子化がついに解禁—労働基準法施行規則の改正ポイント
法改正・政府の取り組み契約書雇用契約
