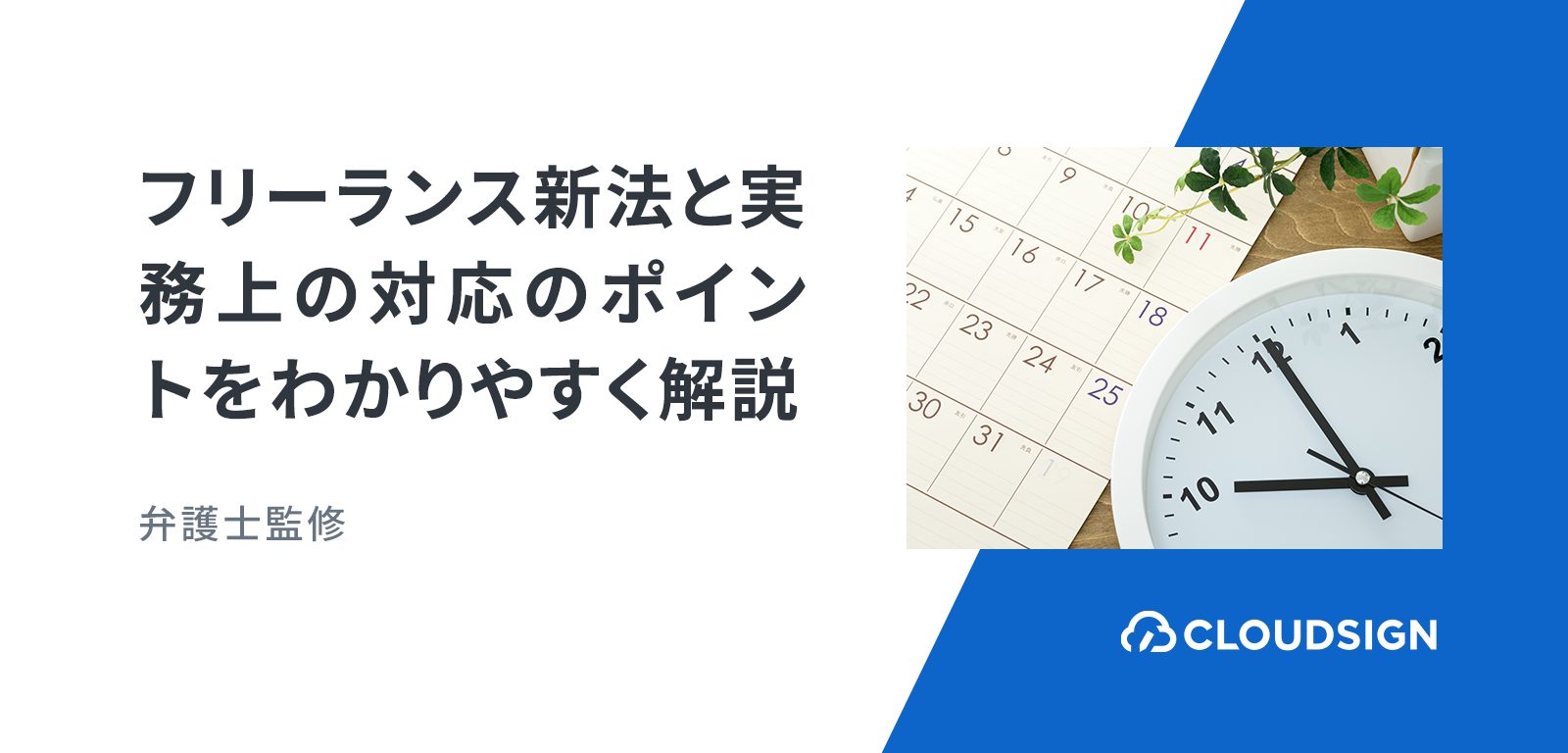フリーランス新法と下請法の違いとは?企業がとるべき対応も解説
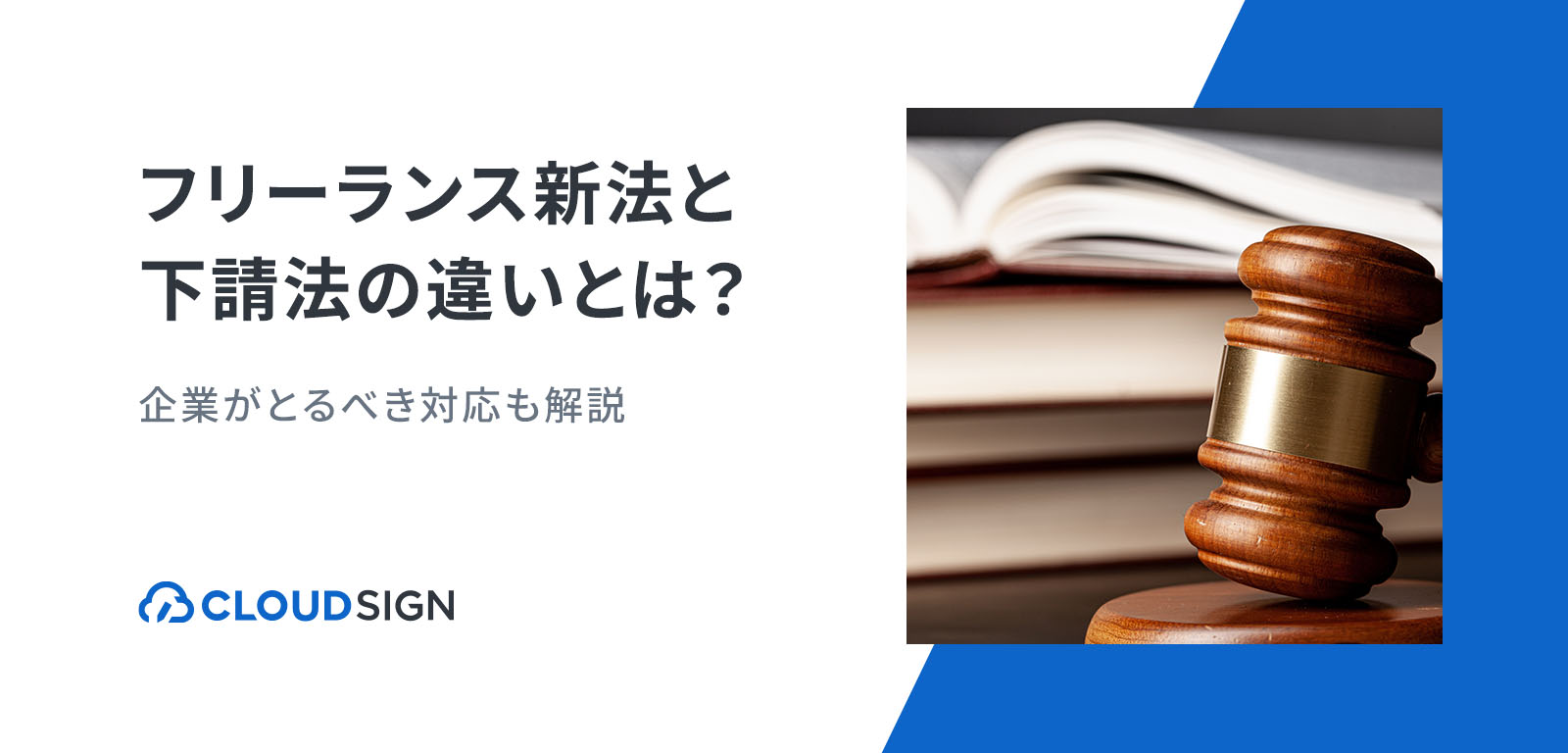
本記事では、フリーランス新法と下請法の違いを詳しく解説します。
2024年11月に施行された「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」は、フリーランスとの取引において企業側に契約書面の交付や報酬支払い期限の明示などを義務付けるものです。一方、従来からある「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」は、製造や修理、情報成果物の作成などを委託する際に適用され、主に代金の支払遅延や減額行為を規制しています。
両者は一見似ているようで、適用される取引内容や保護対象、企業側の義務に違いがあるため、現場で混乱が生じがちです。
本記事では、これらふたつの法律の具体的な規制範囲や内容の違いを整理し、企業がとるべき方法をわかりやすくまとめました。外部の組織やフリーランスに業務の一部を委託している企業の担当者様はぜひ参考にしてください。
なお「クラウドサイン」のようなクラウド型の契約管理サービスを利用すれば、業務効率化を図るとともに法規制に基づいた必要事項を漏れなく記載できるため、電子契約に興味がおありの方は「電子契約の始め方完全ガイド」を無料でダウンロードして活用してみてください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)フリーランス新法とは
フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)とは、企業とフリーランスの間における取引の適正化と、就業環境の整備を目的として、2024年11月に施行された法律です。
フリーランス新法が導入された背景には、フリーランスの働き方が広がる一方で、発注側とのトラブルが相次いでいる実態があります。日本総合労働組合連合会が2021年に実施した調査によると、フリーランスの約4割が「報酬の不払いや遅延、事前の説明不足、不当な契約解除」など、発注側との何らかのトラブルを1年以内に経験していると回答しました。
こうした実態を受け、フリーランス新法では、発注側に対して「報酬額や納期などの書面等による明示義務」「報酬の支払い期限の設定」などのルールを定めています。これにより、フリーランスが安心して働ける環境の整備を目指すとともに、企業側にも責任ある対応が求められるようになりました。
実際、2025年3月にはフリーランス新法が施行されてから初めて、フリーランス新法が定める取引条件の明示義務などに違反したとして行政指導がされています。今後も企業はこの法律の内容を正しく理解し、契約書や発注フローの見直しを行なうことが重要となります。
なお、フリーランス新法の概要や実務上の対応のポイントを知りたい方は下記記事もご一読ください。
フリーランス新法と下請法の違い
フリーランス新法とよく混同される法律として、新法施行以前から存在する下請法(下請代金支払遅延等防止法)があります。
フリーランス新法と下請法は、いずれも企業同士や企業と個人間での取引の適正化を目的とする法律です。そのうえで、フリーランス新法は、不利な立場に立たされるケースが多いフリーランスの地位向上のため、下請法よりも適応範囲や規制内容が大きくなっているという特徴があります。
具体的には、フリーランス新法は以下のような点において下請法と異なります。
- 資本金にかかわらず全ての企業が規制対象となる
- 自社向けの役務提供の委託も規制対象となる
- フリーランスの就業環境も規定している
具体例を交えて解説します。
資本金にかかわらず全ての企業が規制対象となる
フリーランス新法と下請法の大きな違いの一つが、規制対象となる発注者の範囲です。
下請法では、原則として発注元の資本金額に応じて適用の有無が決まります。たとえば、資本金1,000万円以下の企業が個人事業主に業務委託する場合、下請法の適用対象外となるケースもあります。
一方で、フリーランス新法では、発注者の資本金の大小にかかわらず、すべての企業が対象となります。そのため、フリーランスに対して業務を委託する場合、零細企業や個人事業主を含む全ての発注者が、法的義務を負うことになります。
これにより、フリーランスとの取引を行なうすべての企業が、契約内容の明示や報酬の支払い期限など、一定のルールに従う必要があり、法令遵守の重要性が高まっています。
自社向けの役務提供の委託も規制対象となる
下請法では、主に「製品や成果物を納入する取引」が対象となり、最終的に第三者へ提供される業務に関する委託が前提とされています。
そのため、社内資料の作成やWebサイトの更新など、発注元が直接使用する目的での業務委託は下請法の適用外となることが多く、フリーランスが不利な条件で取引せざるを得なかったケースがありました。
しかし、フリーランス新法では、発注先が企業自身のために役務を提供するケースも規制対象になります。具体的には、以下のような自社向けの役務提供にあたる委託も、すべてフリーランス新法が適用されます。
- 自社の宣伝・広告物の写真撮影
- 自社向けの業務マニュアルのライティング
- 自社のWebサイトの更新
- 社内で用いるための外国語文書の翻訳
- 自社のビジネスに関する法的助言
など
つまり、成果物が第三者に渡るか否かに関係なく、フリーランスに業務を委託する時点で法律が適用され、契約内容の明示や報酬の適正な支払いが求められるのです。
フリーランスの就業環境も規定している
下請法は、あくまで「取引の公正性」や「代金支払いの遅延防止」など、商取引に関する規制を主眼としています。一方で、フリーランス新法は、それらに加えてフリーランスの働き方や就業環境の整備にも踏み込んでいる点が大きな特徴です。
具体的には、発注者に対して「育児・介護などの事情に配慮する義務」や「ハラスメント防止措置の義務」など、労働環境に配慮した対応が求められます。雇用関係にないフリーランスが法的な保護を受けづらかった状況を踏まえ、個人事業主であっても安心して継続的に働ける環境を整えることを目的としています。
以上のように、フリーランス新法は、取引上の保護だけでなく、就業者としての立場にも配慮した包括的なルール設計がなされています。
フリーランス新法における企業側の義務項目
フリーランス新法については、具体的には企業側の義務項目として以下が挙げられています。
- 書面などによる取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
- 7つの禁止行為
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に関する体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示
それぞれについて、公正取引委員会の資料を参考に、わかりやすく解説します。
書面などによる取引条件の明示
フリーランス新法では、企業が業務を委託する際に、契約内容や取引条件を通知する義務があります(フリーランス新法第3条)。取引条件については「書面または電磁的方法(メール・PDF・SNSのメッセージ等)」で明確に記載する必要があり、口頭での提示は認められません。
具体的には、企業は業務委託をしたらただちに以下の9つの項目を提示することが求められます。
①給付の内容
②報酬の額
③支払期日
④業務委託事業者・フリーランスの名称
⑤業務委託をした日
⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日
⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
⑧(検査をする場合)検査完了日
⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
これにより、口頭やあいまいなやり取りによる誤解やトラブルを未然に防ぎ、フリーランスが不利な条件を押し付けられない環境を目指しています。明示書面を交付しなかったり、必要事項が記載されていなかったりした場合は違反となります。そのため、業務委託を活用する際はテンプレート化やチェックリストの整備が必要です。
報酬支払期日の設定・期日内の支払い
フリーランス新法では、報酬の支払いに関しても明確なルールが定められています。発注者は契約時点で支払期日を明示しなければならず、原則として業務完了後から60日以内に報酬を支払う義務があります(フリーランス新法第4条)。
また、フリーランス新法においては、下請法にはない「報酬支払の再委託30日ルール」が追加されています。これは、元委託業者A→受託業者B→フリーランスCといった形で再委託が行なわれる場合に限り、元委託業者Aは受託業者Bに対して支払い期日の30日以内に報酬を支払わなくてはならないという決まりです。
受託業者がさらにフリーランスに業務委託をするケースはよくあります。しかし、元委託業者からの支払いがなされないまま再委託分の報酬を支払わなければならないとなると、受託業者にとっては大きな経済的負担となります。結果として再委託先のフリーランスの機会損失にも繋がるため、受託業者は契約時に必要事項を明示すれば例外的に30日以内の支払いを受けられるわけです。
報酬の遅延や未払いは、フリーランスの生活や経営に大きな影響を与えるため、期日内の確実な支払いが求められます。
企業担当者は、支払いフローの整備や期日管理を徹底しながら、会計部門との連携を強化することで、法令違反を防ぎ、信頼ある取引関係を維持するよう留意しましょう。
参考:フリーランス・事業者間 取引適正化等法 - 公正取引委員会
7つの禁止行為
フリーランス新法では、取引の公正性を確保するため、企業側に対して以下の7つの行為を禁止しています。
①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
③返品(受け取った物品を返品すること)
④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
これらの行為はフリーランスの経済的安定や業務の継続性を著しく損なうものであり、違反すれば是正命令や公表などの行政処分の対象となります。
企業側が契約内容の変更や中止を行なう際には、必ず合理的な理由を挙げた上でフリーランス側の同意を得る必要があり、業務委託の基本ルールとして厳守することが求められます。
募集情報の的確表示
フリーランスを公募する際には、企業は業務内容・報酬・納期・取引条件などを正確かつ分かりやすく表示する義務があります。
たとえば、曖昧な表現や誇大な報酬提示、実際と異なる納期や内容の記載などは、不当表示として問題視されます。公正取引委員会は、実態と異なる好条件を掲示して応募後に条件を引き下げる行為や、業務量の不透明な表記を不適切としています。
取引開始前から適切な情報を提示することで、フリーランスが業務の可否を判断しやすくなり、契約後のトラブル防止にもつながります。企業は募集要項や求人内容を見直し、内部で複数チェック体制を設けることが推奨されます。
育児介護等と業務の両立に対する配慮
フリーランス新法では、フリーランスに対して6ヶ月以上の業務を委託している場合、フリーランスからの申し出に応じて、委託者が育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
6ヶ月未満の業務を委託している場合でも、配慮が求められます。配慮の例としては、以下の対応などが挙げられます。
- 妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする
- 育児や介護などのため、オンラインで業務を行なうことができるようにする
- 一方的な業務量の増加や、短納期の強要など生活を圧迫する行為は控える
この規定は努力義務ではありますが、配慮を怠った結果トラブルや苦情が発生した場合、発注者の企業イメージや信頼に影響を与える可能性があります。
フリーランスは労働者ではないため、法的保護が薄いという前提のもと、企業側が自発的に多様な働き方への理解と配慮を示す姿勢が重視されています。
ハラスメント対策に関する体制整備
フリーランス新法では、発注者に対してパワハラ・セクハラなどのハラスメント防止措置の整備が義務付けられています。
具体的には、フリーランスに業務を委託する企業には以下のような体制が求められます。
- 従業員に対してハラスメント防止のための研修を行なう
- ハラスメントに関する相談の担当者や相談対応制度を設けたり、外部の機関に相談への対応を委託する
- ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ正確に事実関係を把握する
引用元:公正取引委員会フリーランス法特設サイト|公正取引委員会
社内規定やマニュアルの整備、社員教育の実施も含め、フリーランスにとって安全な業務環境を提供することが必要です。
中途解除等の事前予告・理由開示
災害などやむを得ず予告ができない場合やフリーランス側に契約の不履行があった場合などを除き、企業側から業務委託契約の解除(中途解除)・停止(不更新)を行なう際には、事前にその理由と時期を通知することが義務化されています。
具体的には、フリーランスに対して6ヶ月以上の業務を委託しており、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、少なくとも30日前までに①書面②ファクシミリ③電子メール等による方法でその旨を予告しなければなりません。
急な契約終了や連絡なしでのキャンセルは、フリーランスにとって経済的ダメージが大きく、他の仕事への影響も及ぼします。突然の契約解除や一方的な仕事の打ち切りは、訴訟などの法的な問題を引き起こすリスクもあるため、絶対に避けなくてはいけません。
契約書上に解除条件を明記しておくことも有効であり、あらかじめ双方向の理解を形成しておくとトラブル回避につながるはずです。
フリーランス新法の施行に伴い企業のとるべき対応
フリーランス新法の施行によって、フリーランスの権利が守られる一方で、業務を委託する企業側としては従来とは異なる対応をしなければいけないケースもあります。
ここでは、フリーランス新法に適応するために企業がとるべき3つの対応について具体例を挙げながら紹介します。
従業員への周知・教育を徹底する
フリーランス新法の施行に伴い、企業がまず取り組むべきなのが、法の内容と自社の対応方針について、従業員への周知・教育を徹底することです。
業務委託を行なう現場担当者や人事・総務部門のスタッフが、法の対象範囲や義務項目を正しく理解していないと、知らずに違反行為を行なってしまうリスクがあります。報酬の支払い期限や書面での契約条件提示など、業務の現場で求められる実務対応を具体的に伝える研修を実施し、ガイドラインやマニュアルを整備することが大切です。
特に発注担当者が複数いる企業では、情報共有がバラつく可能性があるため、社内ポータルや共有シートなどを用いて統一的な管理体制を築くことが、適切な運用につながります。
委託先が特定受託事業者に該当するか確認する
自社が委託している外部パートナーが特定受託事業者に該当するかどうかを確認することも重要です。
具体的には、以下の2つの要件を今一度チェックしましょう。
①従業員を使用しない(代表者1名のみの)個人事業主または法人格である
②自らの名前・屋号で継続的に業務を請け負っている
企業側の判断ミスにより、対象外と誤認したまま契約してしまうと、法令違反となるリスクがあるため注意しましょう。
契約書に必要事項が記載されているか確認する
フリーランス新法の施行により、発注者はフリーランスとの契約に際し、契約書や発注書などに必要な取引条件を明示する義務を負うようになりました。
書面または電磁的記録(メール・PDFなど)で、業務内容、納期、成果物の内容、秘密保持の有無といった事項を正確に記載し、相手に提示する必要があります。これらが未記載または曖昧なまま契約を締結すると、後のトラブルに発展したり、行政指導や違反認定を受ける恐れがあります。
まとめ
本記事では、フリーランス新法と下請法の違いや、フリーランス新法施行後に企業がとるべき対応などについて詳しく解説しました。
日本社会全体として柔軟な働き方が促進されていくなかで、今後業務委託を有効活用しようと検討している企業担当者様も多いはずです。フリーランス新法の規制内容を正しく理解し、法規制を反映した業務契約を結ぶことが、企業の利益を守りリスクを回避するうえで重要です。
従来は口頭やメールのみで済ませていた業務委託についても、文書化と記載内容のチェックが必須となるため、契約書テンプレートの見直しや、法務部門によるダブルチェック体制の構築が求められます。
「クラウドサイン」のようなクラウド型の契約管理サービスを利用すれば、業務効率化を図るとともに法規制に基づいた必要事項を漏れなく記載できるためぜひ活用してください。
クラウドサインは導入社数250万社以上、累計送信件数1000万件超の実績を持つ電子契約サービスです。「どのように導入するのが良いかわからない」「社内で承認を得るためにどうしたらいいかわからない」といった導入時によくいただくお悩みを解決するサポートも充実しています。
なお、クラウドサインでは契約書の電子化を検討している方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)
加藤 高明(かとう たかあき)
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
この記事を書いたライター