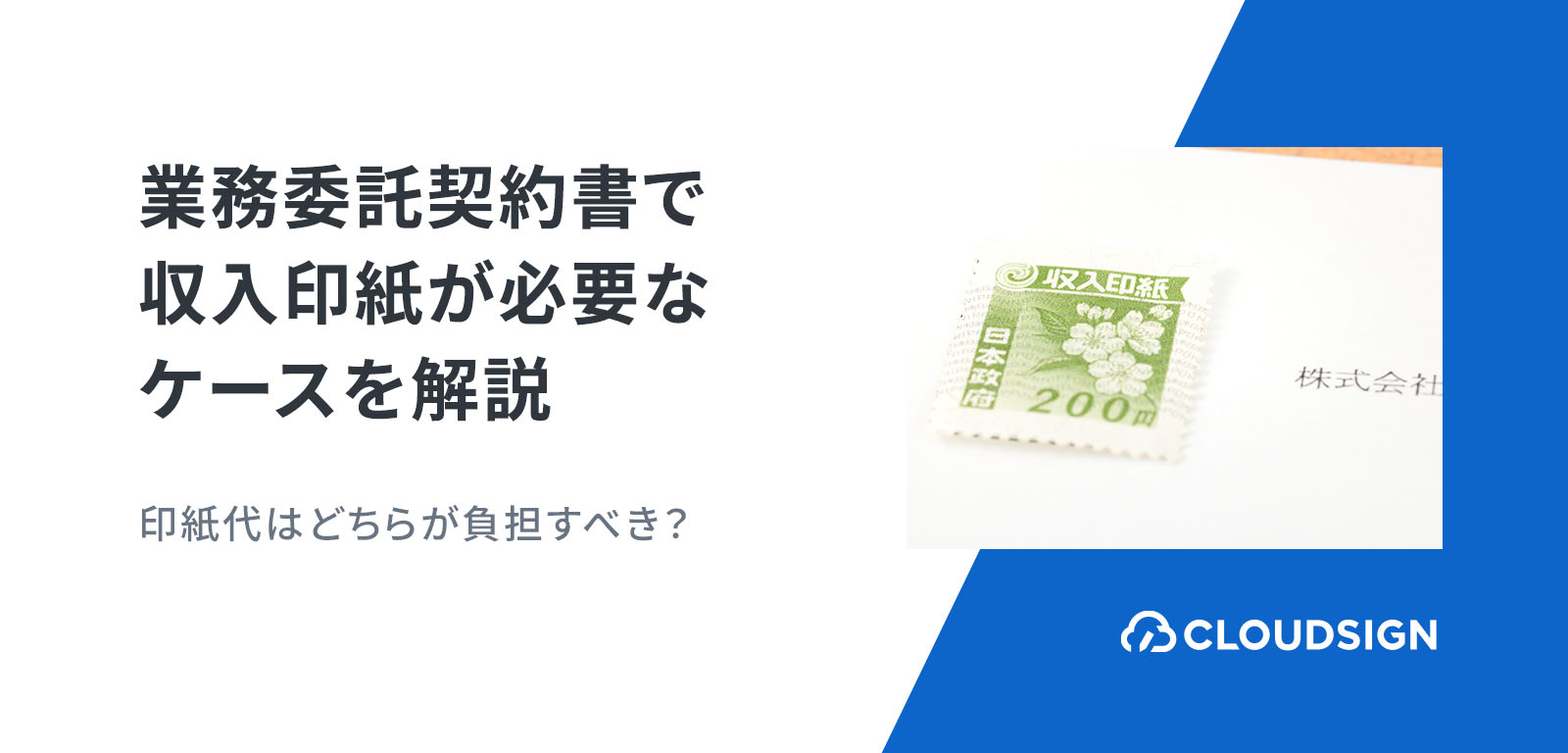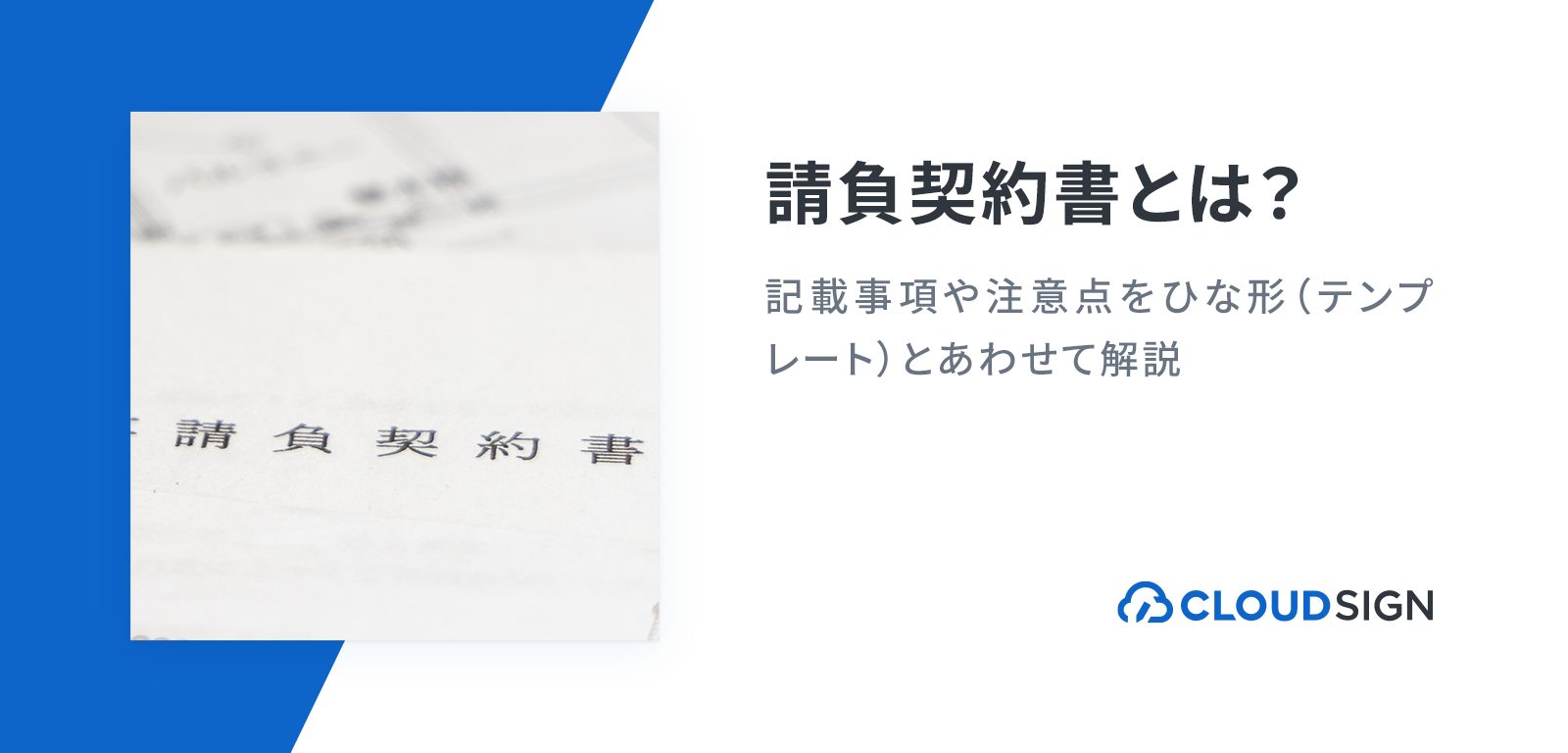業務委託契約と雇用契約の違いを解説
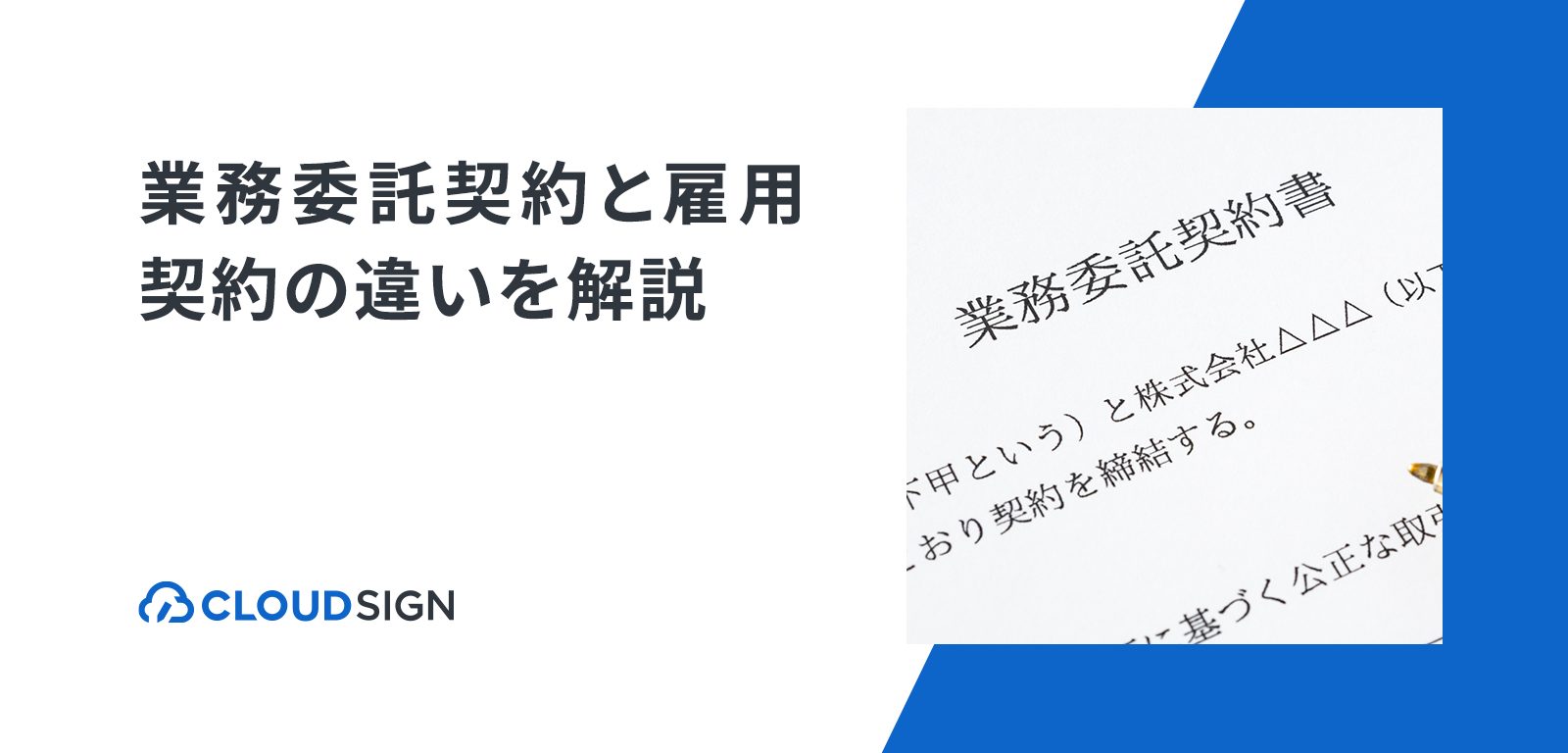
業務効率化や人的リソースの確保のために、業務委託契約を活用する企業が一定数存在しています。コロナ禍によるリモートワークの普及などの影響もあり、昨今ではフリーランスとして副業または本業で企業と業務委託契約を結ぶ人が増えてきています。
そこで、本記事では業務委託契約と雇用契約の違いや見分け方を解説します。また、記事後半では業務委託契約における委託側・受託側双方のメリット・デメリットや、業務委託契約締結時の注意点を紹介します。
業務委託契約の導入を検討している企業担当者の方や、フリーランスとして働こうとしている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
業務委託契約と雇用契約の違いとは?
業務委託契約は、企業や組織が業務の一部または全てを外部の企業や個人に委託する際に結ぶ契約全般を指す呼称であり、法律で定められた定義は存在しません。一方、雇用契約は民法第623条により定義されている契約であり(該当の条文は下記)、労働者が使用者である企業や個人の指示に従う対価として賃金を受け取る契約を指します。
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
働く側の視点から業務委託契約と雇用契約を比較すると以下のようにまとめられます。
・雇用契約:企業や人に所属して指示に従い、対価として賃金を得る
・業務委託契約:双方対等な関係の元仕事を受任し、対価として報酬を得る
雇用契約と業務委託契約は、労働力に対し対価を支払うという意味では似ていますが、いくつかの相違点があります。
次項では、業務委託契約と雇用契約の違いを詳しく解説します。なお、業務委託契約について詳しく知りたい方は「業務委託契約書とは?意味と役割や必要項目を解説【ひな形Wordファイル付】」もご一読ください。
報酬や賃金を支払う側と支払われる側の関係性が異なる
業務委託契約と雇用契約では、報酬や賃金を支払う側と支払われる側の関係性に大きな違いがあります。
雇用契約においては、支払う側(使用者)と支払われる側(労働者)は主従関係にあり、労働者は使用者の指揮命令の下で労働力を提供します。この場合、使用者は労働者に対して一定の労働時間や業務内容を指示し、労働の対価として賃金を支払います。さらに、雇用契約においては社会保険や労働保険への加入が義務付けられ、労働者の福利厚生が保障されます。
一方、業務委託契約では、両者は対等なビジネスパートナーの関係にあるといえ、報酬を支払われる側(受託者)は特定の業務や成果物を提供する義務を負います。業務委託契約では、業務遂行の方法やスケジュールについて受託者が自由に決定することができます。そのため、報酬は労働時間ではなく、成果物や業務の完成度に基づいて支払われるケースが一般的です。
また、業務委託契約では雇用契約のような福利厚生や保険の適用はなく、受託者は自己責任で税金や保険を管理する必要があります。
業務委託契約では労働法が適用されない
業務委託契約では、雇用契約と異なり労働法の適用を受けません。雇用契約では、労働基準法をはじめとする労働法規が適用され、労働者の労働条件や権利が保護されています。たとえば、最低賃金の保証、残業代の支払い、休憩や休日の付与など、使用者に対して厳格な規定が定められています。
一方、業務委託契約はあくまで業務や成果物の提供に関する契約であり、労働者としての権利保障は受けられません。そのため、契約書に記載されている内容が契約履行のすべてを定めるものであり、報酬額や支払い条件、納期などは当事者間で自由に設定され、契約に基づき成果物の納品や役務の遂行を実施します。
また、業務遂行中の事故やトラブルに対する責任も、受託者自身に帰することが一般的です。
このような違いにより、業務委託契約に従事するフリーランスや個人事業主は、労働時間や作業環境に縛られることは少ない反面、自己責任のもとで業務を遂行しなければならないといえます。
業務委託契約と派遣社員は何が違う?
業務委託契約とよく混同されやすいものとして派遣社員があります。業務委託契約と派遣社員の違いは、主に契約形態と労働条件にあります。
業務委託契約では、受託者は発注者から依頼された業務を遂行し、その成果物や業務内容に対して報酬を受け取ります。受託者は発注者の指揮命令を受けず、業務遂行の方法やスケジュールを自分で決定できます。
一方、派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業の指揮命令の下で働きます。派遣社員は派遣先企業の業務環境やルールに従いながら業務を遂行し、派遣元の会社から賃金の支払いを受けます。業務委託契約とは異なり労働法の保護を受けられるため、派遣社員は最低賃金や残業代の支払い、社会保険加入などの権利が保障されています。
ただし、派遣先の企業に所属する形となるため、一定のルールや規律に従う必要があります。
業務委託契約はあくまで外部の人間として企業と契約しますが、派遣社員の場合は派遣先の企業に所属する形となる契約である点が大きく異なるため理解しておきましょう。
業務委託契約に含まれる3つの契約形態
業務委託契約とは、法律で定められた定義はなく、「請負」「委任」「準委任」の3つの契約形態を総称した呼び方です。これら3つの契約については、以下のように簡単にまとめられます。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 請負契約 | 業務の完成や成果物の納品により報酬を受け取る契約 |
| 委任契約 | 法律行為に関する役務の遂行による成果物や役務自体に対して報酬を受け取る契約 |
| 準委任契約 | 法律行為以外の事務作業や開発業務などに関する委任契約 |
業務委託契約として扱われる3つの契約形態それぞれについて、特徴や具体例などを交えながら簡単に紹介します。
①請負契約
請負契約は、民法第632条に基づく契約形態で、受注者(請負人)が特定の成果物や業務を完成させる義務を負い、発注者(注文者)はその対価として報酬を支払う契約を指します。
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
請負契約では、成果物の完成が義務の中心となり、その完成に至る過程や方法については受注者の裁量に委ねられます。
建築工事やソフトウェア開発、デザイン制作、WEBライターなど、明確な成果物の納品を目的とした業務委託契約の大半が請負契約といえるでしょう。
請負契約では、契約の基準を満たした成果物が完成し、発注者に引き渡された時点で契約が履行されるため、未完成の場合や不備がある場合には報酬が支払われなかったり、修正が求められたりする可能性があります。
また、請負契約では受注者が独立して業務を遂行するため、労働法の適用はなく、発注者が具体的な作業工程や方法などについて指揮命令を行うことはできません。そのため、受注者には自主的に作業を計画し、実行する能力が求められます。同時に、発注者に対して成果物の品質や納期を確実に守る責任も負うこととなります。
請負契約を締結する際は、成果物の基準や納期・報酬基準などについて詳細に取り決めた契約書を作成し、トラブルを防ぎつつスムーズな契約履行を実現することが推奨されます。
企業が外部の個人や組織と請負契約を結ぶ際に発行する請負契約書について知りたい方は「請負契約書とは?記載事項や注意点を解説 建築工事請負契約書のテンプレート付き」も参考にしてください。
②委任契約
委任契約は、民法第643条に基づく契約形態で、受任者(業務を引き受ける側)が発注者(委任者)の指示に従って法律行為を行うことを約束する契約です。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
典型的な例として、弁護士に訴訟手続きを依頼する場合や、司法書士に登記を依頼する場合などが挙げられます。また、企業の法律顧問として法務全般の業務を遂行する顧問弁護士も、基本的には委任契約です。
委任契約の特徴として、法律行為を遂行すること自体が義務であり、成果の完成は必須ではない点が挙げられます。たとえば、弁護士が依頼された裁判で必ず勝訴する義務はなく、仮に委任者の希望通りの成果が得られなかったとしても、契約に基づいた報酬を受け取れます。
ただし、受任者には善管注意義務が課され、委任者の利益を最優先に考え、職務を誠実に遂行することが求められます。
委任契約では、法律行為が中心となるため、一般的な業務委託契約よりも特化した業務内容が多く、委任者と受任者の信頼関係が重要となります。
③準委任契約
準委任契約は、民法第656条に基づく契約形態で、委任契約に似ていますが、法律行為に限定されず、事実行為を含む業務を遂行する契約です。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
たとえば、コンサルティング業務、システム運用保守、データ入力業務などが準委任契約として扱われるケースが多いです。
準委任契約では委任契約と同様に、成果物の完成が義務ではなく、受任者が依頼された業務を遂行すること自体が目的となります。このため、請負契約のように完成した成果物に対して報酬が支払われるのではなく、業務遂行の過程に基づいて報酬が決定される場合が多いです。また、受任者には善管注意義務が課され、委任者の利益を守りながら業務を誠実に遂行することが求められます。
準委任契約について詳しく知りたい方は、「準委任契約とは?書き方と記載事項や類似した契約との違いを解説|ひな形Wordファイル付き」も参考にしてください。
業務委託契約と雇用契約の見分け方
業務委託契約と雇用契約の見分け方として「使用従属性が存在するかどうか」が挙げられます。
使用従属性とは、一方がいずれか一方の指揮命令に従っている関係性を指し、使用従属性が認められた場合は雇用契約、使用従属性が無く受託側と委託側が対等な関係である場合は業務委託契約とみなされます。そのため、契約形態としては業務委託契約であっても、発注者が受注者に対して指揮命令を行っていると判断された場合は雇用契約とみなされる可能性があります。
具体的には、使用従属性があるといえる状況は以下のとおりです。
・勤務時間や勤務場所が拘束されている
・報酬が時間基準である
・契約内容に記載されていない業務がある
・業務内容や遂行方法に関して強い指揮関係がある など
原則として、業務委託契約は受託者と委託者は対等な関係のもと契約を結ばなくてはいけません。そのため、業務を発注する側が受託側の業務の遂行方法やスケジュールなどについて指示をしている場合は、雇用契約とみなされる可能性が高いでしょう。
【委託側】業務委託契約のメリット・デメリット
業務委託契約における委託側にとってのメリットとして、コストの効率化と柔軟な人材活用が挙げられます。
業務委託契約では雇用契約と異なり、社会保険料や福利厚生の負担が発生しないため、コスト削減が可能です。また、単純作業であれば外注に任せて人員を上手くコントロールできるほか、特定のスキルや専門知識が必要な場合には、必要な期間だけ外部の専門家を活用できるなど、様々な場面に合わせて即戦力の確保が容易です。
さらに、成果物ベースの契約が多いため、納期や品質に重点を置きやすく、業務効率が向上します。長期的な雇用リスクを避けつつ、必要な業務に集中できる点も利点といえるでしょう。
一方で、専門性が高い分野を外注すると業務委託費用が高くなるリスクがあります。また、業務委託は外部の個人や企業に業務の遂行を任せることになるため、業務に関するノウハウが企業内に蓄積されづらい点も懸念材料といえます。
加えて、委託側には契約履行中の業務に直接的な指揮命令ができないという制約があるため、期待通りの成果物が得られないリスクがあり、成果物の完成度を保証するためには契約内容を詳細に定める必要があります。
【受託側】業務委託契約のメリット・デメリット
業務委託契約における受託側にとってのメリットは、業務遂行の自由度の高さです。
業務委託契約では、受託者は発注者の指揮命令を受けずに、自分のペースで業務を進められます。また、複数の案件を掛け持ちできるため、収入源を多様化しやすい点も魅力です。独立性の高さが、キャリアの成長や新たなビジネスチャンスを生む契機になることもあるでしょう。
一方で、受託側にはキャリアや収入が安定しないというデメリットがあります。雇用契約のような安定した収入は保証されず、案件が途切れた場合には収入がゼロになるリスクがあります。また、社会保険や税金の手続きは自己負担で行う必要があり、これらの管理に時間やコストがかかります。
業務委託契約をメインとして継続して収入を得るためには、スケジュール管理能力や交渉力、そして専門的なスキルが求められるほか、持続的に仕事を獲得するための営業力も必要といえるでしょう。
一般的に、フリーランスの場合は企業に雇用されるよりも立場上保護されないケースが多いといえます。その一方で、コロナ禍を経てリモートワークなどの多様な働き方を選択する方が増えています。そこで、フリーランスの方の労働環境向上のために「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス新法)」が令和6年11月に施行されました。
これにより、取引条件の明示やハラスメント対策の体制整備などが委託側に義務づけられ、今後はさらにフリーランスの方が社会で活躍しやすい環境が整えられていくでしょう。フリーランス新法について知りたい方は「弁護士監修|フリーランス新法と実務上の対応のポイントをわかりやすく解説」もご一読ください。
業務委託契約を締結する際の注意点
業務委託契約を締結する際の注意点を紹介します。企業としてフリーランスとの業務委託契約締結を予定している方や、フリーランスとしてこれから企業と業務委託契約を開始する予定がある方は確認しておきましょう。
使用従属性が認められた場合は雇用契約となる
業務委託契約を締結する際、使用従属性が認められると法律上は雇用契約とみなされる可能性があります。
使用従属性とは、受託者が業務の遂行において委託者の指揮命令を受け、その指示通りに働く状態を指します。例えば、勤務時間や場所が厳密に指定されている場合や、業務の進め方や優先順位を細かく指示される場合には、使用従属性があると判断されやすくなります。
雇用契約とみなされた場合、委託者は労働基準法や社会保険関連法令に基づく責任を負う必要があり、最低賃金の保証、残業代の支払い、社会保険の提供などの義務が生じます。
意図せず雇用契約となると、不測のコストや法的リスクが発生する可能性があります。これを回避するには、業務委託契約の条件を明確化し、受託者が指揮命令を受けずに自主的に業務を遂行する独立性を確保することが重要です。
報酬体系や業務内容について明記した契約書を作成する
業務委託契約を締結する際、報酬体系や業務内容について詳細に明記した契約書を作成することは、双方のトラブルを防ぐうえで極めて重要です。
契約書には、業務の範囲、納期、成果物の品質基準、支払い条件、報酬額やその算出基準、契約解除に関する条件などを具体的に記載する必要があります。とくに、報酬体系については、固定報酬なのか成果報酬なのか、支払期限がどの時点か等を明確にしておくことが重要です。
また、業務内容について具体性が欠けていると、受託者が業務範囲外の作業を要求されたり、委託者が期待する成果が得られなかったりする可能性もあるため、業務内容や範囲についても明確に定義しておくことが求められます。
契約書は双方の信頼を築く基盤であると同時に、万が一の際の重要な証拠となるため、慎重に作成しましょう。
まとめ
本記事では、業務委託契約と雇用契約の違い、業務委託契約のメリット・デメリットを解説してきました。
業務委託契約を締結する際は、当事者双方の齟齬を防ぐために業務内容や報酬について明確に定義した契約書の作成が求められます。業務委託契約を電子契約サービスで締結・管理すれば、保管コストの削減に役立つうえ、検索性も向上し必要な時に必要な情報を参照でき、万が一のトラブルの際にも迅速な対応が可能となります。
当社の運営する電子契約サービス「クラウドサイン」は電子署名を電子ファイルに施し、スピーディーかつ安全に当事者間の合意の証拠を残すことのできる電子契約サービスです。導入社数250万社以上、累計送信件数 1000万件超の国内シェアNo1の電子契約サービスとして、業界業種問わず多くの方にご利用いただいております。
契約締結はもちろんのこと、締結した契約の管理も可能なため、契約書管理ツールとしてもお使いいただけます。
なお、クラウドサインではこれから電子契約サービスを比較検討する方に向けて「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。下記リンクから無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。
この記事を書いたライター