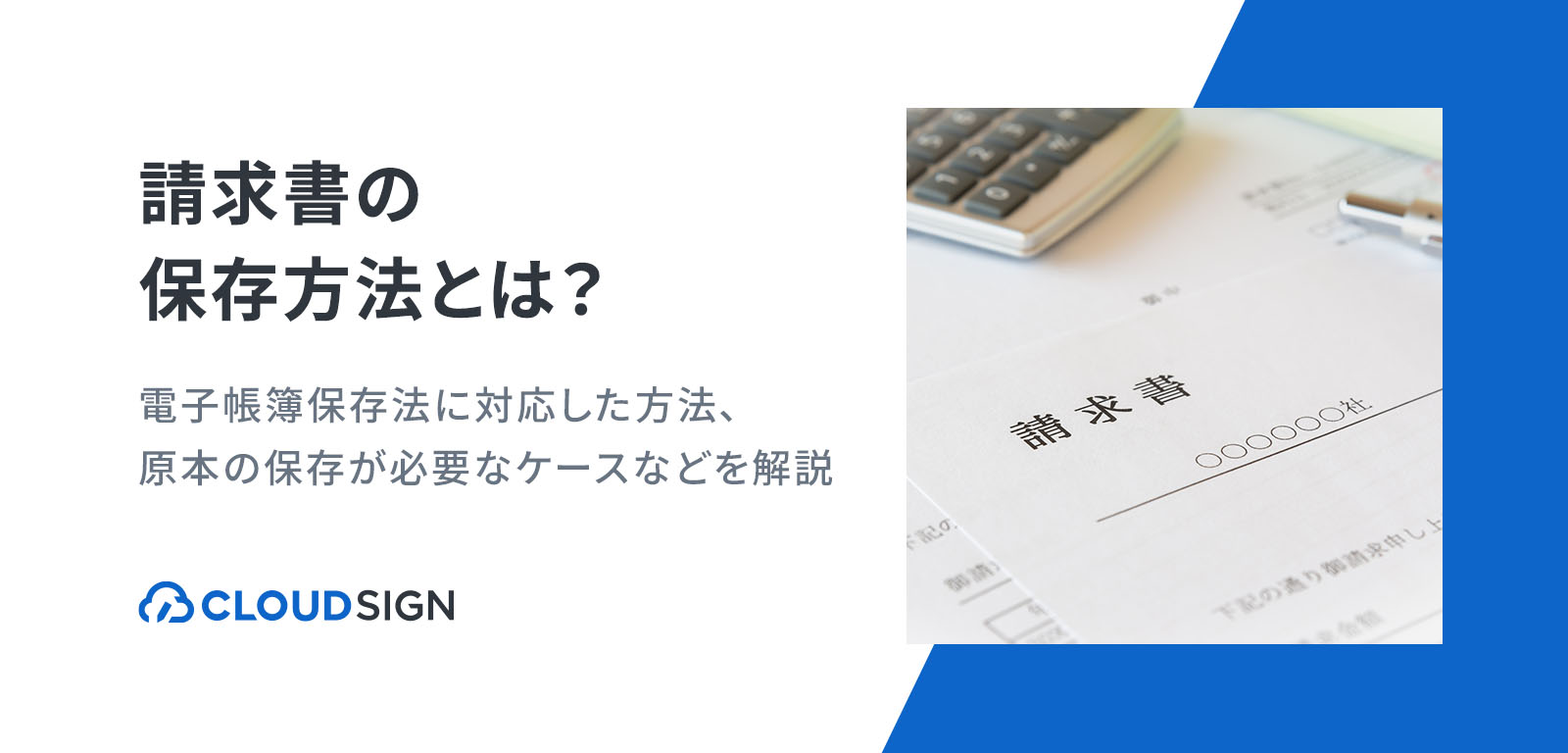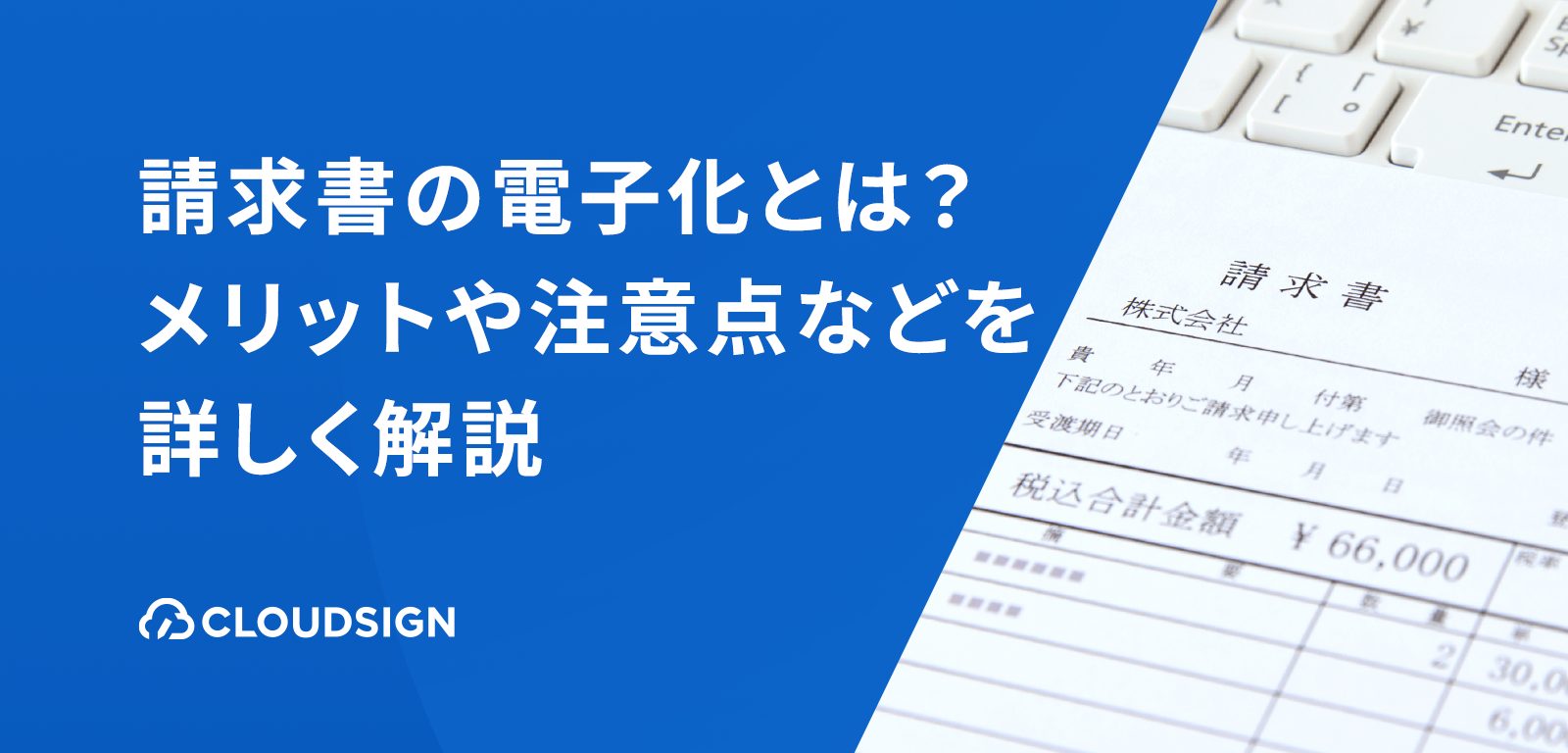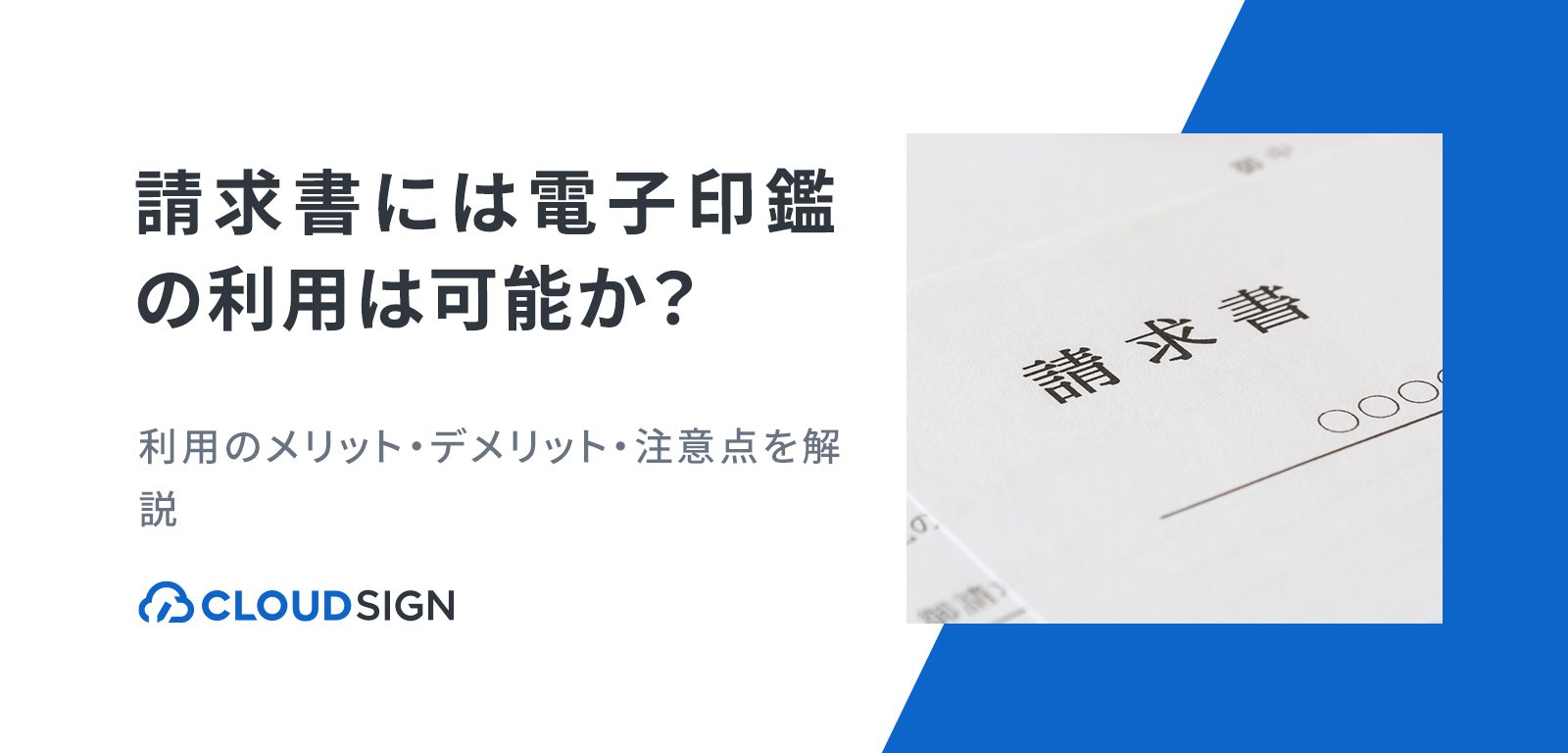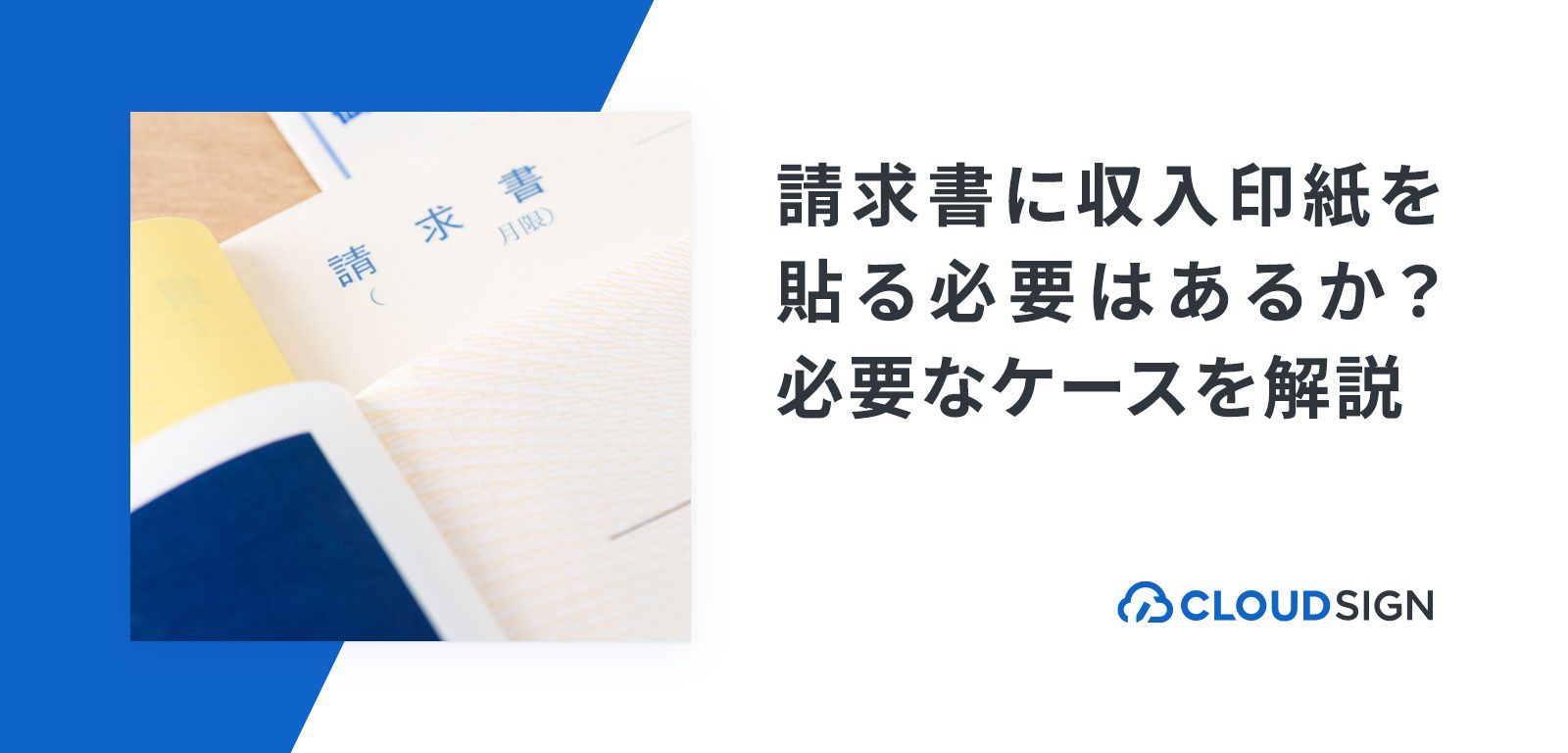電子請求書を導入する場合の案内文の書き方|例文や注意点を解説
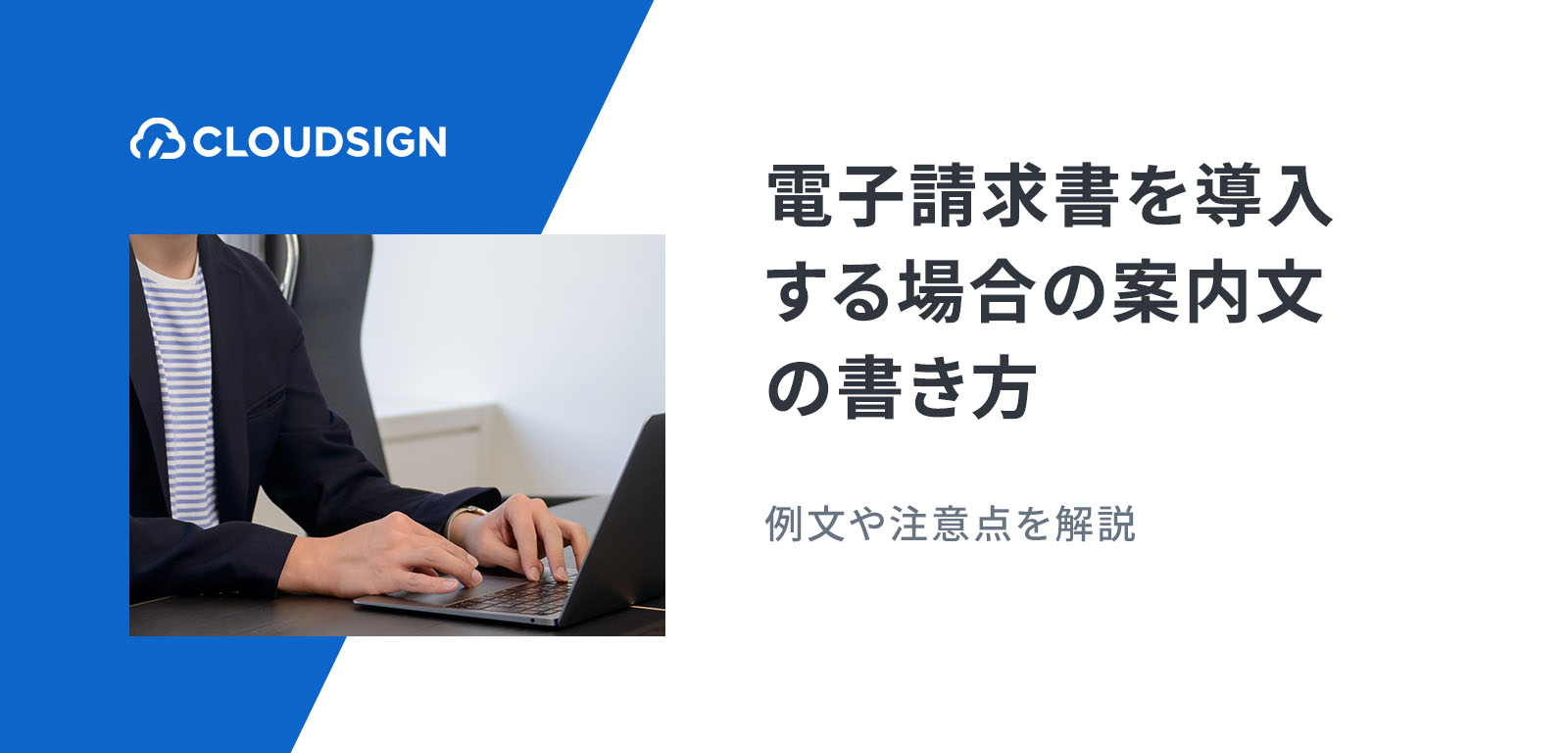
電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が求められる中、電子請求書の導入を進める企業が増えています。
業務の効率化やコスト削減に効果的な一方で、従来の紙による請求書に慣れている取引先にとっては、導入後の運用方法や対応に不安を感じるケースもあります。そのため、電子請求書への切り替えをスムーズに進めるには、なぜ電子化するのかの明確な理由やメリットを取引先に対してわかりやすく説明する必要があります。
本記事では、電子請求書導入時に使える案内文の書き方や例文、記載すべきポイント、注意点などを詳しく解説します。
電子請求書を導入する際は案内文が必須
電子請求書を導入する際には、取引先にその旨を通知し承諾を受けるために、案内文の送付が必須です。
これまで紙の請求書でやり取りしていた取引先にとって、電子請求書への切り替えは業務フローの変更を含め新たな対応を伴う可能性があるため、突然の変更通知のみでは、戸惑いや誤解を招くおそれがあります。
そこで、導入の背景や目的、開始時期、対応してほしい内容などを明確に記載した案内文を事前に送ることが重要です。特に、受領方法が複数ある場合(メール添付、Webシステム経由など)は、具体的な操作方法や問い合わせ先もあわせて案内すると、取引先も安心して対応できるでしょう。
また、インボイス制度や電子帳簿保存法といった法令への対応が背景にあることを伝えることで、導入への理解が得られやすくなります。企業間の信頼関係を維持しつつ、スムーズな移行を実現するためにも、案内文は単なる連絡ではなく、説明責任を果たす文書として作成することが求められます。
電子化の案内文に盛り込むべき内容
請求書電子化の案内には、以下の6点を盛り込むことが求められます。
・時候の挨拶・電子化を決定した理由
・電子化導入による取引先にとってのメリット
・電子化の開始日
・システムの説明
・問い合わせ先
それぞれの項目について、盛り込むべき理由や具体例を挙げながら解説します。
時候の挨拶
必須ではありませんが電子化の案内文においても、ビジネスマナーとして時候の挨拶を盛り込むことは重要です。
特に長く付き合いのある取引先に向けては、季節感や礼儀を感じさせる挨拶を冒頭に入れることで、形式的な連絡ではなく丁寧なコミュニケーションを心がけている印象を与えられます。
たとえば、「春暖の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」など、季節に応じた表現を取り入れると好印象でしょう。時候の挨拶に加えて、日頃の取引に対する感謝の言葉を添えることで、案内文全体に丁寧で誠実な印象を与えられます。
単なる業務連絡ではなく、関係性を大切にしていることを伝える一文として、時候の挨拶は取り入れておきたい要素です。
電子化を決定した理由
案内文では、請求書の電子化を実施する背景や決定理由を明確に説明することが信頼を得るために不可欠です。
理由が不明確なままでは、取引先にとって突然の対応変更に戸惑いや不満が生じる可能性があります。電子化の背景としては、「ペーパーレス推進」「電子帳簿保存法やインボイス制度への対応」などが挙げられます。
電子化を決定した理由を丁寧かつわかりやすく記載すれば、企業としての合理的判断であることが伝わるでしょう。
電子化導入による取引先にとってのメリット
電子化によって自社側が得られる効率化やコスト削減だけでなく、取引先にとってのメリットを明確に伝えることが、導入案内文での重要なポイントです。
受け手が自分たちにとってどんな利点があるのかを理解できなければ、対応への協力や理解は得にくくなります。
たとえば、「受領までの時間が短縮される」「過去の請求書を電子データで簡単に検索・保存できる」など、具体的な実務上の利点を伝えれば、導入への前向きな姿勢を引き出すことが可能です。
特に、今までどおりの作業よりも簡単・便利と感じてもらえるような視点を意識して、相手に寄り添った案内を心がけましょう。
電子化の開始日
電子化を導入するにあたっては、実施開始日を明確に示すことが不可欠です。
開始日が曖昧なままでは、取引先がいつから対応を変えるべきか分からず、混乱や請求書処理のトラブルにつながる恐れがあります。案内文には、「○年○月○日以降に発行する請求書より、電子送付に切り替えさせていただきます」など、具体的な日付を明記しましょう。
期日が迫っている場合は、「開始日までにシステム登録をお願いいたします」など、取引先側の準備が必要な旨もあわせて伝えるとより親切でしょう。
システムの説明
電子請求書の導入にあたっては、使用するシステムや運用方法についての説明も欠かせません。特に初めて電子請求書に対応する取引先にとっては、送受信の方法や必要な操作が分からないことは不安要素となります。
具体的な利用手順や形式、ログイン方法、操作マニュアルの案内などを記載することで、スムーズな移行を促せます。可能であれば、操作ガイドやFAQページへのリンクもあわせて案内すると親切です。システム説明を丁寧に行なうことで、問い合わせや混乱を減らし、円滑な電子化を実現できるでしょう。
問い合わせ先
電子化に関して不明点があった場合に備え、問い合わせ先の明記も非常に重要です。
システムの使い方や開始日の認識違いなど、取引先からの質問や確認は一定数想定されるため、事前に対応窓口を明示しておくことで、混乱や誤解を防げます。
案内文には、電話番号・メールアドレス・担当部署名などを具体的に記載し、「ご不明点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください」といった一文を添えると、より丁寧な印象になります。
問い合わせ先を明確にすることで、電子化の導入後も安心してやり取りができる信頼関係を維持できるでしょう。
電子請求書の案内文の例文
請求書を発行する側が取引先に対して電子化を通知する案内文の例を紹介します。時候の挨拶や導入目的など、適宜調整してご利用ください。
| ○○ご担当者様
拝啓 春暖の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 さて、この度弊社では業務の効率化およびペーパーレス化の推進、また、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応を目的として、請求書を電子発行に移行する運びとなりました。 つきましては、これまで郵送でお送りしていた請求書を、今後はPDF形式にてご登録いただいたメールアドレス宛に送信させていただきます。貴社におかれましても、請求書の受け取りが迅速になるほか、過去1年分の請求書をいつでも閲覧・ダウンロードできるようになるといったメリットもございます。 ご不明点やメールアドレスの変更、紙での発行をご希望の場合などがございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 敬具 記
ご不明点やご質問などございましたら、下記担当者までご連絡をお願い申し上げます。 【お問い合わせ先】 株式会社◯◯ 経理部 請求書電子化担当 TEL: Email: |
電子化・ペーパーレス化を案内する際のポイント
ここでは、請求書の電子化・ペーパーレス化を案内する際のポイントを解説します。
電子化開始までのスケジュールを伝える
電子請求書への移行をスムーズに進めるには、電子化開始までの具体的なスケジュールを明確に伝えることが重要です。スケジュールが曖昧だと、請求書の受け取り漏れや処理遅延といったトラブルの原因にもなりかねないためです。
導入文は、「電子請求書の発行は○月○日より開始」「○月○日までに登録手続きを完了してほしい」など、対応期限・運用開始日を記載することで、取引先が対応しやすくなります。移行期間の確保も重要なので、導入開始の2〜3か月前には案内文を送るのが好ましいでしょう。
システム登録やテスト送信など、事前に行なうべき対応事項がある場合には、それらの締切や作業手順もあわせて記載するようにしましょう。
電子化の理由やメリットを明記する
案内文では、電子化の背景や目的、取引先にとってのメリットを明確に伝えることが大切です。理由が不透明なままだと、取引先は「なぜ対応しなければならないのか」と疑問を持ち、協力を得られにくくなる可能性があるためです。
たとえば、「電子帳簿保存法やインボイス制度への対応」「環境配慮によるSDGs推進」など、企業としての取り組みとともに説明することで納得感が得られやすくなります。
取引先側にも「請求書の紛失リスクの低減に繋がる」や「素早い受け取り・処理が可能になる」といった具体的なメリットを伝えることで、電子化に対する前向きな対応を促せるでしょう。
自社と取引先の双方が使いやすいシステムを選ぶ
電子請求書の運用においては、使いやすさ・分かりやすさが重要です。
導入するシステムは、自社の業務フローに合っているだけでなく、取引先にとっても操作が簡単で対応しやすいものであることが理想です。
たとえば、シンプルな画面設計やPDFの自動送信など、負担の少ない送受信方法が整っているかが選定のポイントとなります。取引先が多数ある場合は、多様な形式(メール添付、ポータルサイト経由など)に対応しているシステムを選ぶことで、柔軟に運用できるでしょう。
導入前にはテスト送信の機能やデモ画面で確認する機会を設けるなど、操作性を十分に検証し、自社と取引先双方にとってストレスのない運用を実現することが大切です。
サポート体制を整える
電子化を導入する際は、システムの操作や請求書の受け取り方法について取引先からの問い合わせが増えることが予想されるため、万全なサポート体制の整備が必要です。
案内文には、必ず担当部署の連絡先や問い合わせ窓口、受付時間などを明記し、何かあればすぐに相談できる環境を整えましょう。可能であれば操作マニュアルやFAQ、動画マニュアルなどを用意し、取引先に共有すると、問い合わせ対応の負担も軽減されます。
特に導入初期は、想定外の質問やシステムトラブルが起こることもあるため、社内の対応体制を事前に決めておくと安心です。迅速で丁寧な対応は、取引先からの信頼にもつながるでしょう。
押印形式を確認する
電子請求書に切り替える際には、「請求書に印鑑が必要かどうか」「電子印鑑は認められるか」といった押印に関する確認も重要なポイントです。
法的には、請求書に印鑑は必須ではなく、押印がなくても問題はありませんが、取引先によっては従来どおりの押印を求める慣習や社内ルールが存在する場合があります。
そのため、電子印鑑付きPDFの提供や、必要に応じて押印画像を挿入した形式での送付など、相手に応じた柔軟な対応方針を事前に検討しておくことが望ましいでしょう。
案内文には「電子印鑑を押印したPDF形式で送付します」や「押印が必要な場合はご連絡ください」などの表記を加えると、混乱を防ぎ、円滑な運用が実現できます。
取引先が電子化に対応できない場合は紙面で送付する
電子請求書の導入にあたっては、すべての取引先が即座に対応できるとは限りません。
高齢の経営者や中小事業者、インターネット環境が整っていない取引先などにとっては、紙でのやり取りが必要なケースもあるでしょう。そのため、電子化を基本としつつも、「紙での送付を希望される場合はご連絡ください」といった例外対応の案内も記載することが大切です。
柔軟な対応姿勢を示すことで、取引先との信頼関係を損なわずにスムーズな移行が可能になります。紙送付を希望する取引先には、利用可能なサポートを個別に案内することで、将来的な電子化のハードルを下げることにもつながります。
まとめ
本記事では、請求書を電子化する際の案内文に盛り込むべき内容や、案内文を送付する際のポイントなどについて詳しく解説しました。
電子帳簿保存法の改正などにより、今後どの業界においても請求書などの契約に関する書類は電子化が推進されていくと予想できます。
業務効率化を目指して請求書も含めた契約書類のDX化を考えるのであれば、契約書の電子化もおさえておくべきといえます。適切な形での契約管理を実現するなら、クラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」の利用をご検討ください。
無料ダウンロード


クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター