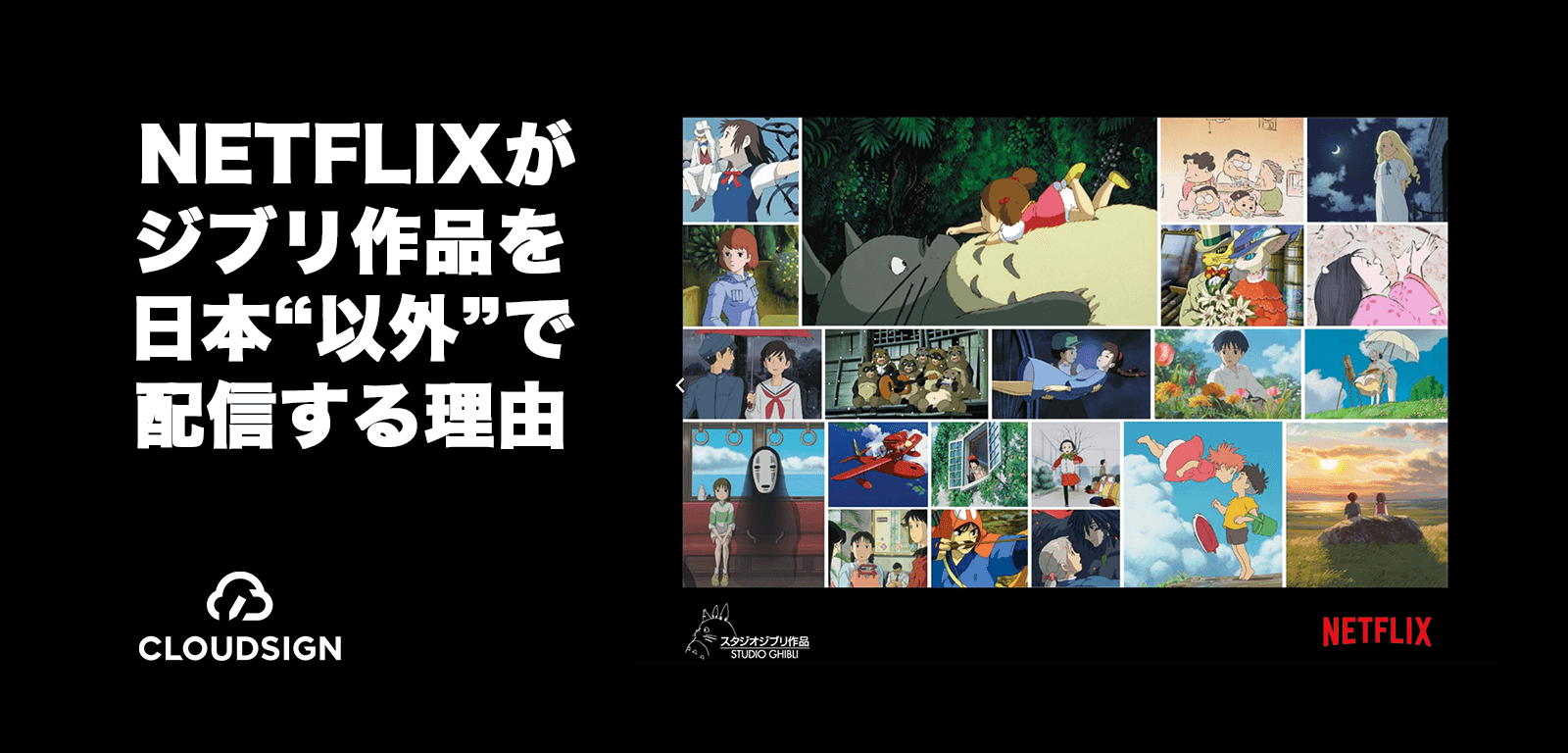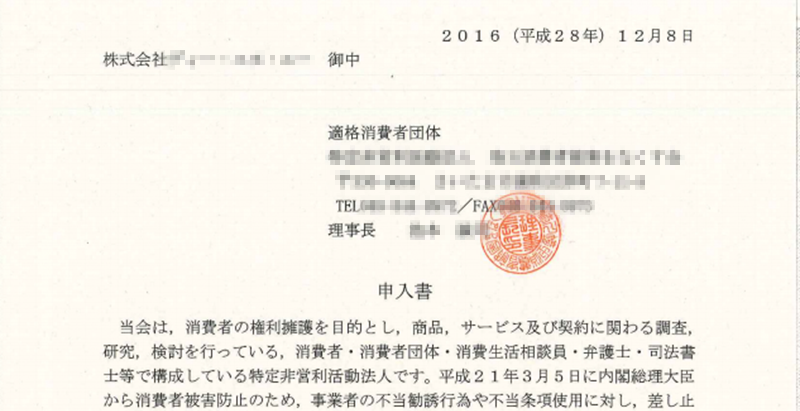オプジーボ特許料問題 交渉戦術の選択に残る2つの疑問

締結済みのライセンス契約の料率が不当だとして、製薬会社との交渉経緯を社会に公表した京都大学の本庶特別教授。報じられる紛争の経緯をおさらいしつつ、一般的なライセンスフィーの合意形成プロセスに照らして浮かんだ疑問を整理してみました。
契約締結済みの特許料についての紛争
がん治療薬の発明でノーベル賞を受賞した京都大学の本庶佑特別教授と小野薬品工業との間で、ライセンスフィーの妥当性についての紛争が発生 しています。
ノーベル医学・生理学賞を受賞した京都大学特別教授の本庶佑さんは10日、会見を開き、受賞理由になったがんの免疫療法の薬を共同で開発した製薬会社の小野薬品工業に対し、特許料の配分が不当に低く抑えられているとして契約の見直しを求めていることを明らかにしました。これに対して小野薬品工業は、「会見の全容を把握できていないので、コメントは差し控えさせていただきます」としています。
同席した弁護士によりますと、契約に基づいて本庶さんに分配される特許料はおそよ26億円で、小野薬品工業から正確な説明や情報提供がないまま契約を結んでいて、本来は1000億円に達してもおかしくないとしています。
別の報道では、2014年(平成26年)9月の販売開始から昨年12月までの4年で約2890億円、2024年には世界市場での年間売上が100億ドル(10兆円)に上るという推計もあるオプジーボ。

発明者である本庶さんは、裁判は望まないとしながらも、2890分の26、つまり1%未満に契約上設定された特許ライセンスフィーの見直しを求め、社会に対し訴えるという手段に出ました。
特許のライセンスフィーはどのように定められるのか
医薬品の発明に限らず、ビジネス上有用な発明を特許化し企業にライセンスすれば、対価としてフィー(特許料)を受け取ることになります。
一口にライセンスフィーと言っても、その受け取り方には、下図のようにさまざまなパターン・組合せがあります。

ですが、医薬品のように製品化の成否や販売量・売上が予想しにくい製品の場合、Bの「出来高にリンクしない実施料」は選択せず、Aの「出来高にリンクする実施料」、原則としては料率実施量(percentage royalty)が選択されることがほとんどでしょう。
問題は、そのパーセンテージの具体的数字についてどう合意するか です。
ライセンスフィーには「相場」がある
開発にかかった費用を積み上げるなど、開発者が最低限回収したい金額はかんたんに計算できます。しかしそれを超える部分、発明の付加価値にあたる部分をどう値付けするかは難しい問題です。
そのため、最終的には、見えない価値をもすべて包含して合意が形成されている(はずの)「業界相場の料率」 が参照されます。
たとえば、他人の特許権を気づかないうちに侵害してしまった場合、特許権者から特許料を請求されることがあります。この場合事前の契約が無いため、特許料をいくら支払うべきかで相当に揉めるわけですが、交渉や訴訟において、本来ライセンス契約が締結されていれば支払われるべきライセンスフィーの相場を示す根拠として必ず持ち出されるのが、以下2冊の文献です。
- 『ロイヤルティ料率データハンドブック』(経済産業調査会,2010)
- 『実施料率(第5版)』(発明協会研究センター,2003)
これらの文献には、業界別・製品別アンケート調査等により判明したライセンスフィー料率水準 が記載されています。

今回問題となっているオプジーボが属する 医薬品カテゴリのライセンス料率相場、いずれの文献でも3〜5%が中央値 となっています。
会見で公表された情報によれば、本庶特別教授側が受け取っているのは1%。こうした相場観との乖離を契約の後で認識し、不満を抱いたとしても無理はありません。
教授側の戦術選択に残る2つの疑問
とはいえ、将来のライセンス料を契約で合意した以上、それに対して異論を述べるのは後出しジャンケンです。教授サイドも、そのことをわかっているが故に、ライセンス料の水準を公表し「弱者」の保護を訴えるという戦術を選んだのでしょう。
ところが、この戦術には2つの大きな疑問を感じます。
疑問1:契約時に大学のサポートはなかったのか?
本庶特別教授は、NHKの単独インタビューに対し、
契約が、正確な説明、正確な情報の提供なくして、我々が判断を誤らされたという認識を持っており
つまり、1%のライセンス料率を合意した契約の成立自体は争わないが、特許料の一般相場等の情報を知らないまま、不当に安いライセンス料率を認めさせられたのだという主張をしています。
当時の事情は当事者のみが知りうることではあるとはいえ、立派な成人が契約書を締結しながら、後で「こんなはずではなかった」と契約を無かったことにしようというのは、客観的に見て無理筋です。
さらに、バックには京都大学という機関もついていたはずです。本庶特別教授が契約を締結したとされる2006年(平成18年)時点、京都大学にライセンス契約をサポートする体制はなかったのか という点です。通常、産学連携の研究であれば、知的財産の権利化を大学としてサポートし、本庶特別教授が契約に深い理解がなかったとしても、これをサポートしうる立場ではなかったのでしょうか。
京都大学は、2003年(平成15年)度時点で大学知的財産本部整備事業の対象となっていたことが資料からも確認でき、何らかのバックアップを行う準備はあったものと考えられます。

当時、本庶特別教授がこうした大学の体制に従い支援を受けた上で契約していたのかどうかについても、論点になりそうです。
疑問2:ライセンスフィーを開示する行為は秘密保持義務違反とならないか?
もう一つの疑問が、こうした紛争経緯を社会に公開するにあたって 本庶特別教授がライセンスフィーと料率水準を開示したことが、契約上の秘密保持義務の違反に当たらないのか という点です。

特許ライセンス契約のような知的財産に関する契約において、秘密保持条項が存在しないということは考えられません。そうなると、ライセンスフィーや料率が秘密情報として守秘義務の対象に当たるかが論点となります。
守秘義務の対象に当たらないとなれば、このような事態においても効力を発揮しえないNDAを結ぶ意味を世の中に問うものとして、一方で当たるとなれば、企業に与えたレピュテーション・ダメージをどのように算定するかについて、貴重な先例となりそうです。
画像:cassis / PIXTA(ピクスタ)
(橋詰)